2024/02/05/月
寄稿:メディヴァの歴史
無人島に街をつくれ ー 先駆者列伝19:認知症ケア向上に、体験グラス大活躍
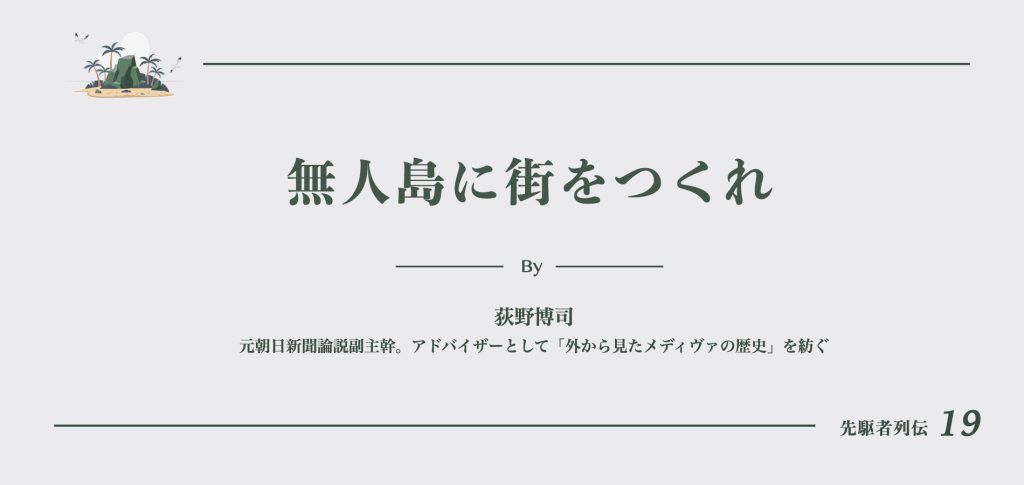
認知症体験のARグラスを使った衝撃は大きかった。
iPhoneを組み込んだヘッドセットを装着すると目の前の様子は一変した。辺りは暗く、視野は一気に狭くなる。遠近感がつかめず、目の前の椅子に腰かけるにも手探りで位置を確かめずにいられない。どうしても前かがみになり、横から声を掛けられ手を取られると、誰なのか見えない不安から身がすくんだ。
「拡張現実」と訳されるARは実際の光景にデジタル情報を重ね合わせることで、特別な状態に置かれた際の視界を再現できる。人気ゲームなどに使われるVR(仮想現実)はデジタル空間を体感するもので、実際にはない別世界ということがあらかじめ分かっている。それと異なり、ARは周囲の様子を映し出しながら、デジタル情報を重ね合わせて加工している。
体験したヘッドセットには、認知症患者が見る光景を再現するプログラムが入ったスマホが仕込まれていた。いうならば認知症体験グラスである。いま、このAR機器は患者の立場からの医療や介護という視点から、医療者の行動を変えようとしている。
メディヴァと一緒に開発したのは慶応大学メディアデザイン研究科(KMD)の南澤孝太教授や院生のエリザベス・チェン(沈襲明)さんだった。南澤先生は「身体的経験を伝送・拡張・創造する身体性メディアの研究開発と社会実装」の研究を重ねている。何やら難しいが、たとえば紙コップに石を入れて揺すった時に、そのデータを別の紙コップに伝え、そちらでも振動を感じさせる触覚の遠隔操作技術(ハプティクス)はその一つだ。
東京・竹芝のラボで実体験させてもらったが、たしかに空コップなのに石が飛び跳ねているようだった。最先端のIT技術を実用化することに積極的な研究室で、その延長線上にメディヴァのAR機器は誕生した。
KMDにおける認知症への取り組みは5年ほど前、米国からの留学生の思いからスタートした。自らのお祖母さんは認知症だが、炊事をする映像を見せるうちに会話が始まったり、犬を触っていると名前が思い出されたりする。その体験から認知症患者のために最先端の技術を生かせないかと考えていた。医療と介護に一体で取り組み、ITの導入に積極的なメディヴァに行きつき、交流が始まった。
南澤先生は「施設でいろいろな機器を体験してもらった。滝下りや水浴びなどのハプティクス技術を使った疑似体験で体が動くことも確認できた」と振り返る。介護士とのコミュニケーションに「触る」という体験が加わると記憶が呼び戻せることを、メディヴァが運営支援する「かんたき(看護小規模多機能型居宅介護)」で試行したこともある。
認知症は、中核症状(記憶障害や見当識障害など)は治らなくても、適切な対応やケアによって徘徊や暴力といった周辺症状の発生は抑えられる。一般的に「問題行動」と言われているものの多くは周辺症状ということになる。適切な対応やケアの第一歩は、「認知症で苦しむ方がどういう世界に暮らしているのか」を理解することだ。認知症に優しい環境デザインを研究開発している英国スターリング大学でも、環境整備とケア研修は両輪とされている。
メディヴァからKMDに提案したのが、AR技術を活用した認知症の疑似体験システムだった。その頃、木内大介シニアコンサルタントらも認知症ケアの向上には医療関係者の理解が欠かせないと考え、効果的な取り組みを模索していた。医療や介護の現場の人々が認知症の理解を深めて適切な対応をとるには、患者の視点で身の回りを見ることができたら効果的だという直感からだった。
認知症を学ぶことに重点を置いて考えてみると、VRは所詮は作り物の世界であり、それだけで人の行動を変えることは難しい。それならば拡張現実のARはどうだろうか。こちらは実際の現場における疑似体験を通して、医師、看護師らは自らの環境や行動を振り返ることができる。南澤先生に相談してみたところ、海外では暴力や虐待問題への対応策として、被害者の視点から状況を体験させる手法があるということも教えてもらった。
そうした時に追い風が吹く。経産省が2020年度から3年間つづけたサービス産業強化事業費補助金制度である。本シリーズの第12回で紹介した水海道さくら病院での環境デザインの実証と併せてARグラスの開発が「認知症対応包括プログラム」として採択された。
KMDの修士課程にいたエリザベスさんが技術面の開発を担った。メディヴァからは、これまでに現場で積み上げた知見や研究論文などを提供し、一緒に議論を重ねた結果、「視覚障害」のほか、周囲のことに影響を受けやすく目の前のことに集中できない「注意障害」、模様や反射の誤認、奥行き知覚の低下など「空間認知、視覚認知障害」の三点に絞り、システムづくりに取り組むことになった。彼女も認知症のお祖父さんがいただけに開発には力が入り、2020年11月の着手から半年で原型機を完成させた。
21年12月、第1号機が世界の舞台でお披露目を果した。コロナ禍の真っ最中だったが、東京国際フォーラムで開催されたコンピューターグラフィックスの祭典「SIGGRAPH ASIA 2021」で来場者に体験してもらえた。反響は大きく、「認知症だとこう見える。AR体験が衝撃でした」「かなり日常生活を送るには不便、かつ苦痛を伴うだろう」など、当時の取材レポートには驚きが綴られている。
並行して水海道さくら病院など医療施設での研修会を始めた。ARグラスを被った医療職からは「おじいちゃんが何故手探りで椅子に座るか分かった」「前に立って話しかけることが大切なことが理解できた」「良かれと思って院内の照明に力を入れたけど、かえって混乱することが分かった」などの声が聞かれ、学びに繋がることが確認できた。
メディヴァ主催の体験会に参加した120人へのアンケートでは、ほぼ全員が認知症への共感度が高まったと答えた。とくに看護師やリハビリテーション職は全員が高い評価を与えた。
体験と学びを経験してもらったのちに、認知症に優しい環境デザインを提案すると先方の反応が違う。認知症デザインがどれだけ効果的なのかは、ARグラスをかけて歩いてみれば一目瞭然である。スターリング大学認知症サービス開発センターと連携し、認知症介護に向き合ってきたメディヴァは心強い最新機器を手に入れた。
いま認知症ARグラスは4台に増え、医療関係者の研修会などに貸し出している。開発したプログラムをもとにメディヴァのコンサルタントがインストラクターとして実地体験を指導している。機器を活用して研修などを運営するファシリテーターの育成コースも設けた。青木朋美マネージャーのもと新たな介護事業部のサービスメニューとして動き出した。
23年度の実績を紹介しよう。23年9月にオープンした福岡市の認知症フレンドリーセンターでは来場者の3分の1にあたる900人ほどが体験し、地元ニュースでも報じられている。病院での研修は3箇所で400人ほど、さらにはプライマリケア連合学会での展示体験と大活躍である。
高齢化による認知症の広がりは、各国とも避けて通れない。若者社会とされてきたアジア諸国も大きく変わろうとしている。2年前には日本国際交流センターが設けたアジア健康長寿イノベーション賞の準大賞にも選ばれた。アジア9か国・地域から応募があり、その中でも地域の高齢者ケアに貢献すると評価されたのだ。
エリザベスさんは23年4月にドイツ・ハンブルグで開催された人間とコンピュータの相互関係に関する国際学会(CHI)で認知症グラスの開発を発表した。ともすれば最先端の技術を誇る報告が多いなかで、実際の認知症ケアの向上につながる研究は注目を集めた。
すでに視覚に加えて聴覚も加えた機器を開発できないか、といったアイデアが出ている。これからどんな進化を遂げるのか。何とも楽しみである。