RECRUIT BLOG
2025/04/07/月
寄稿:メディヴァの歴史
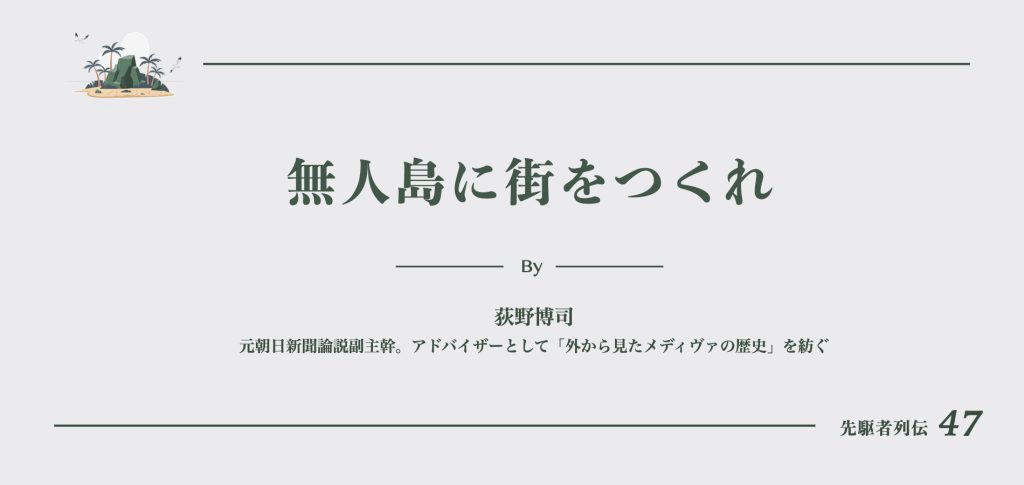
まずはおさらいから。コミュニティ&コミュニティホスピタル(CCH)事業が目指すのは単なる治療の場にとどまらず、予防や健康増進、さらには地域づくりまでを視野に入れた、新しい病院像だ。医療の質を充実させながら、同時に経営の持続可能性も高めていくというバランスの取れた戦略が求められている。
そこでは総合診療を中軸に据え、来院する患者さんだけを相手するのでなく、こちらから病院の外に出て地域の要望に真摯に向き合う姿勢が求められる。医師や看護師だけでなく、リハビリテーション専門職、社会福祉士、薬剤師、管理栄養士など、様々な専門職がチームとなって住民をサポートする。
CCH事業への取材を重ねるなかで、実現のカギを握るいくつものキーワードに出会った。
まずは〈可塑性〉。自在に形を変えることができるという意味で、同善会のコミュニティホスピタル化を実現した小笠原雅彦副院長はこの言葉を繰り返した。同じCCH病院でも、立地によって取り組みは異なる。同善会がある東京都内のように医療機関の多いところでは、社会的な課題、たとえば患者が抱える精神疾患や通院への障害などの事情を踏まえた細かな対応が求められ、専門医に橋渡しする役割も期待される。一方、連載(11、12回)で紹介した茨城県の水海道さくら病院のように周辺に医療機関が少ない地域であれば、二次救急や小児救急を手厚くすることが重要となる。
小笠原医師は「柔軟な医療コーディネート力と変化に対応できるだけのキャパシティの掛け合わせが重要になる」と説明する。可塑性を可能とするのが総合診療医である。特定の疾患・症状の分野に特化するのではなく、文字通り「総合的に患者を診る」ことができるからだ。そのうえで、顧客の立場に寄り添いながら、必要とする商品やサービスを提供していく〈マーケットイン〉の発想がポイントになると付け加えた。
医療もサービス業の一つではあるが、病院が売るものを決め、それを患者が買い取るような取引が当たり前だった。しかし、総合診療医が中心となるCCHでは、医療機関は「あなたの生活を支えるうえで必要な技術とスタッフを用意します」という形態に変わるというのだ。そのうえで患者や家族の意向を優先させ、要望をどうやったら叶えられるかを考えることになる。
同善会では入院してきた患者への対応が大きく変わった。現在は初日の午前中にリハビリ専門職、看護師、ソーシャルワーカー、医師・薬剤師・栄養士がそれぞれ患者や家族から必要な事項を聴き取り、一通りの評価をしたうえで他の専門職と情報を共有する。CCH化の前は入院から2週間後の中間カンファレンスの際に初めてデータを持ち寄っていた。
新しい仕組みに変えたことで患者優先の姿勢がより明確となったうえ、病状の変化にも機敏に対応できる。単に早く退院したいというだけでなく、他に抱えている病気も落ち着かせたい、この機能を回復したいといった要望、さらには社会参加の意思や退院後にどんな生活を目指したいのかも聞く。
今年度から小笠原医師は水海道さくら病院にも通っている。ここで目指しているのは〈横展開〉だ。CCH化に奮闘している小嶋秀治院長を応援するとともに、ゼロから始めた同善会の成果を他に広げる実践の場という面もある。
シーズ・ワンを率いる羽田雅史さんは、それまで在籍した官民ファンドREVIC(地域経済活性化支援機構)で病院再生を手掛けたが、個別再建の限界を感じていた。それだけに多くの病院が横につながるCCH事業はきわめて魅力的だったと振り返る。
全国に展開するのであれば、組織運営や事務処理などの〈標準化〉が欠かせない。その仕組み、パッケージを走りながらでも作らないとならない。単独の再生事業では、複数病院の医療事務の集中処理や共同購買、人材の融通などはできないが、CCHではそれが可能になる。横展開と標準化は車の両輪のような役割を果たすことになるだろう。
羽田さんが推進している事務センターは、その一翼を担うことになる。中小病院では事務担当者が辞めると途端に業務が回らなくなるような事態さえ起こる。そうした弱点を解消していくのが狙いだ。
人手不足が深刻化する中で、簡単に人は採れなくなっている。そこでシーズ・ワンが経理や人事、採用など事務の全体を見るもので、試行的に同善会で始めている。事務部門の担当者の多くを現場から引き揚げて遠隔作業に切り替え、人事や経理のオフィスはなくした。残っているのは小口現金管理と医事課の窓口のみで、シーズ・ワンからは企画担当者や地域活動の専門スタッフが出ているだけだ。すでに水海道さくら病院や後に紹介する本多病院は同じ方向で取り組んでおり、他のCCH病院でも動き出した。
CCHの成否のカギを握るのは〈人づくり〉だと多くの方から伺った。一般社団法人であるCCH協会の最終目標は、教育や研修を通じての医師の育成である。そこで育った医師を全国のコミュニティホスピタルに派遣する仕組みを確立できれば理想的だ。
メディヴァは病院経営の改善にはめっぽう強いものの、医療にかかわる専門職を育成するのは容易ではない。「誰かが育てた人を連れてくるだけでは限界がある。自前で育てる仕組みを作り込む必要がある」というのが小笠原医師の診立てだ。たしかに、地域の医療をよくするには限られた医療人材の奪い合いではなく、総合診療医など中核となる専門職の厚みを増すことが欠かせない。
総合診療医を育てるCCH総診だけでなく、専門医取得から6年目以降の医師を対象にした指導医フェローシップやリーダーフェローシップ研修、各職種横断の教育コンテンツなどをCCHの教育プログラムとして開発したのも、人材育成へのチャレンジということになる。教育には投資が先行してコストがかさみがちだ。総合診療医を最初から育てれば2、3年かかるが、実績のある他科専門医に総合診療の知識もつけてもらえたら、養成の期間は一気に短縮するだろう。
挑戦的な試みを成功に導くうえで、後進のお手本になる〈ロールモデル〉の役割は重要だ。その一人と目されるのが東京・大田区の本多病院で理事長兼院長を務める石川輝医師である。地域に根差した医療の将来像を探るうえで、新人院長の挑戦は注目される。
理事長兼院長とはいってもまだ35歳。当人は医師10年で務まるのかという不安はあったが、小病院でやりたい思いから恩師の紹介に乗ったそうだ。ここは47床を持つ2次救急病院だが、経営の立て直しのためにCCH病院への転換に踏み切った。現在は5人が常勤医で、このうち3人は30歳代の総合診療医。その中の最年少が石川院長である。
昨年11月に着任してからの日々には大きな手応えがある。職場の呑み会のときのみんなの笑顔から、地域への思いを共有したワンチームに変わりつつあると感じたという。目指すのは再現性が難しい臨床で学び、一方で地域の人と一緒になるという理想の実現だ。
以前に人口1万3000人ほどの兵庫県新温泉町にある公立病院で働いた経験を持つ。経営が振るわず有床診療所に変える議論もあったが、自ら議会とも話して3億円あった累積赤字を圧縮することで何とか存続させた。
カメラを下げて街に写真を撮りに出るように心掛けたのは「自分の町なんて」という住民に地元の魅力を再認識してもらうのが狙いだった。地域の光景や人々の暮らしを切り取った作品を外来フロアに飾ったら評判になり、空気が変わった。
「よそもの」「わかもの」「ばかもの」――。地域の復興・再生には、この3つの要素が欠かせないといわれるが、石川医師は「本当だった」と自らの体験を振り返り、今の本多病院でも愛用のカメラを手に街を歩いている。
この3月から1か月半、医師としての診療業務は同僚と調整のうえ、お休みしている。管理者としての職務は続けるが、実質的な育休というわけだ。お嬢ちゃんが生まれたためで、院長が休むのは異例かもしれないが、同じ世代の医師のロールモデルとして決断したという。各地のCCH病院に石川さんのような医師が増えれば、地域社会を支える病院への信頼や親しみは高まるに違いない。
CCH構想では、今後10年間で100病院への直接支援を目指している。22年の同善会以降、これまでに直営6病院がCCHへの転換を進めているが、目標達成までの道のりは遠い。候補の発掘にあたる羽田さんは支援機構時代のつながりも生かして病院再生などのニーズを掘り起こし、さらに進んでCCHへの移行を働きかけている。さらに経営不振が目立つ自治体病院からも相談が舞い込むようになってきた。
一方、コミュニティホスピタルをそれぞれ独自で目指す病院仲間を増やすことも、超高齢社会を迎える日本にとっては重要だ。構想の生みの親である大石さんや小松大介取締役、実務の中心であるシニアマネージャーの草野康弘さん、村上典由さんらは、機会を見てはセミナーや勉強会などを積極的に仕掛けている。この4月にも「中小病院が日本の医療を変革する」と銘打ってコミュニティホスピタルの意義と可能性を訴えるセミナーをオンラインで開催する。こうした勉強会などを通じて関心を持つ病院や医療者のネットワーク「CCHパートナーズ」を広げることが、今後の全国展開には欠かせないだろう。
ただ、目標に近づくためには、これまでの病院再生のやり方だけでは対応できないのは明らかだ。25年間に培った企業文化を守りながら、大規模展開のためには更なる〈仕組み化〉が求められる。
草野さんは「CCHは注目を集めており、医療システム全体の変革に貢献できる可能性を持っている」と胸を張る。人材を育て、テクノロジーを活用し、仕組み化していきながらも、医療の本質である「人を支える」という価値を大切にした組織モデルを広げるには、これまでに挙げたキーワードの一つ一つを丁寧に実践していくほかない。
少子高齢化や過疎化が進むなかで苦境にある中小病院は全国に広がっている。地域包括ケアの拠点として再生を図る理念は魅力的に映るが、それだけの人材やノウハウをどう提供していくのか。外部の出資も募って始まったCCH事業はメディヴァが島の外に踏み出し、新たな地に街をつくることにつながる。
次の25年をにらんだ壮大な挑戦に心からの声援を送りたい。