2024/05/15/水
寄稿:メディヴァの歴史
無人島に街をつくれ ー 先駆者列伝26:多彩な顔ぶれが集った「梁山泊」
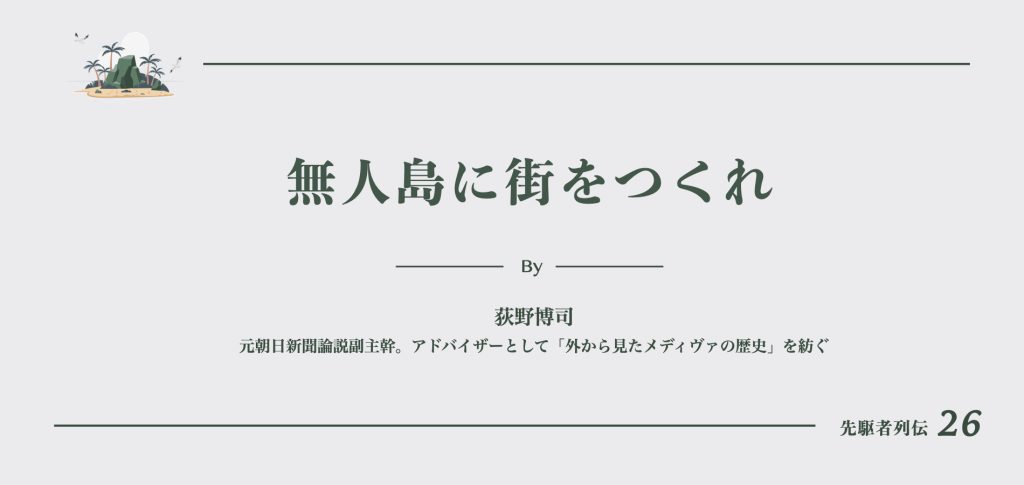
中国明時代の長編小説に「水滸伝(すいこでん)」がある。北宋末期、108人の好漢(英雄)が集まり、世直しに力を合わせる物語だ。江戸時代に日本に伝わって人気を博し、時代や登場人物を置き換えた翻案作品がいくつも生まれている。
その舞台となる地が「梁山泊(りょうざんぱく)」である。原著では好漢らの隠れ里の印象だが、日本では大望を持つ志士が集まり、将来について熱く論じ合う場といった意味が加わっている。メディヴァの歴史をたどると、ここにも梁山泊があった。
2013年。保健事業部が発足する一方、医療機関の再生事業も動き出していた。またイークが開院し、アーバンクリニックの陣容も整ったころだ。診療所の一画にあった桜新町アーバンの在宅医療部の人数が増えたことから、広めのスペースを外部に求めた。周辺では物件が見つからず、用賀駅近くにある朝日生命ビルの2階に事務所を構えた。ただ、フロア全体を使うほどではない。ちょうど同じ時期、現在も本社を置くグレース用賀ビルのオフィスが手狭になったことから、医療機関以外へのコンサルティング業務を担当するメンバーも朝日生命ビルに移り同居することになった。
新オフィスの6割には遠矢純一郎院長をはじめ、医師、看護師、療法士、事務スタッフやメディヴァから派遣されている事務長の村上典由さんらがいた。残りの4割にメディヴァのコンサルタントが座る。間に壁や仕切りはなく、ほぼ一緒に仕事をしている情景である。
新オフィスに入ったコンサルティングチームの守備範囲は、すでに事業として自立している診療所外来、病院コンサル、保健指導サービス以外なら何でもあり。結果として新事業の開発部隊となり、後の企業行政チーム、海外チーム、拡大ぽじえじチームがここから育った。10人足らずの陣容だったが、ワイワイガヤガヤのなかから自由な着想が飛び出し、新しい事業の種が自然と生まれた。
真横に桜新町アーバンの在宅医療部があった効用は大きい。24時間365日、在宅の患者さんを支えている専門職が働いている。昼食時には、MRによるお弁当付きの医薬情報説明会の声が聞こえてくる。「門前の小僧」ではないが、専門職同士の真剣なディスカッションが耳に入る。ちょっとした疑問を横にいる専門職に尋ねると、日頃の実践を踏まえて丁寧に教えてくれる。医療的な知識もさることながら、自然とメディヴァに求められている「患者視点の医療改革」を肌で感じることになり、目線が上がった。
連載の第5回で紹介したiPhoneを電子カルテの情報共有に活かす取り組みが開始され、認知症の初期対応に取り組んだ時期である。桜新町アーバンは日本の最先端を走っていた。朝日生命ビルには、遠矢院長ら専門職の助言を得ようと厚労省や政党、自治体、医療団体、システム会社、在宅クリニックなど全国から幅広い見学者が集まる。メディヴァの方にも同じくアドバイスを求める人たちが全世界かやって来る。双方の訪問者により最先端の情報がもたらされ、それらが結合し、さらに新しい発想に結び付いた。さまざまなアイデアをぶつけ合うのが何とも面白く、エネルギーはすごいものだったと当時を知る人は口をそろえる。
同時に楽しい職場でもあった。当時のメンバーの一人、増崎孝弘さんは朝の勉強会をやるために、炊飯器を持ち込んで朝食を用意したことを懐かしく思い出す。同じフロアでは在宅医療部の木内大介さんの提案で朝の体操タイムやミニ英会話教室が始まった。桜新町アーバンの主導で餅つきもした。2階だと床が抜けるかもしれない、という心配があり、臼や杵を1階の駐車場に移動させてクリニックの患者さんも交えて餅をついた。桜新町アーバンの看護師さんのラブラドール犬ルイちゃんと、大石さんのパピヨン犬のジンジャーも出勤している。ルイちゃんのケージが遠矢院長のデスクの後ろに置かれていた時期もあったほどで、職場に溶け込んでいた。
この環境のなかで生まれたのが、医療機関にとどまらない、企業、行政・自治体、健保組合、海外など幅広いクライアントを抱えるメディヴァの新たな業域である。
当時は地域包括ケアの創成期で病床中心から居宅という流れが見えてきた。医療態勢を整えた地域社会づくりに向けて国から自治体に案件が降りてくる。そのための施策やロードマップ作りにあたっていた増崎さんは大仕事を手掛けることになる。基礎自治体の担当として取り組んだ死亡小票の分析だ。
死亡診断書には性別や生年月日、死亡の日時や場所、死因、看取った医師の名前などが医師によって書き込まれる。それをもとに自治体が作成し、国の統計のもととなるのが死亡小票で、亡くなった方のデータが網羅されている。大石さんらと議論する中で、これは使えそうだという話になった。さっそく自治体に開示請求をお願いして手に入れてみたが、分かりづらいエクセルデータである。
地域包括ケアシステムがどの程度進捗しているかの指標として、自宅で亡くなった数や、割合が重要となる。ただ自宅で亡くなったと書かれていても、そこには自殺や事故も含まれる。地域包括ケアシステムが取り組んでいるのは、そういう死因を除いた純粋な看取りである。正確な「自宅看取り」データをまとめるには中身を読み込んだうえで死因別に分類し、手入力を繰り返すほかない。分からないことは、現場を知る周囲の医師に教えてもらった。
異状死つまり孤独死、事故死を抽出すると、居宅での看取りは自治体が発表している数字よりはるかに少ないことが分かった。さらに地域ごとのばらつきが極めて大きいことも浮かび上がった。2014年ごろから横浜市を皮切りに作業に取り組み、まず11-13年のデータを数カ月かけて分析した成果を報告書にまとめた。増崎さんは死亡小票分析の手法と結果を在宅医療系の学会などで発表し、大きな反響を呼んだ。全国に死亡小票分析が知られるようになり、その後、メディヴァでは千葉県柏市や練馬区などの分析も扱った。
地域包括ケアシステムを構築することは大事でも、課題の存在や大きさ、施策の進捗などについて根拠をもって示さないと納得は得られない。死亡小票の解析で現状が把握できれば、必要な施策を決めるうえでの裏付け資料となる。例えば横浜市青葉区の場合は、高齢化とともに進む多死社会の中で、地元の内科系開業医は平均して年間5名以上を自宅で看取らないと対応が追い付かないことが予測された。また現在の自宅看取りが、一部の診療所に過度に依存していることも分かった。おのずと地域における「在宅療養支援診療所」の増強が課題として浮かび上がることになった。
その後、増崎さんはメディヴァを離れ、医療分野のテックベンチャーでプロジェクトマネージャーをする一方、ゲイ3人によるボーカルユニット「八方不美人」のメンバーちあきホイみとして歌手活動に励んでいる。ライブやテレビにも出演し、今年の秋にはソロアルバムを出す。何とも多才だが、女装歌姫(ドラッグクイーン)としてのキャリアのきっかけは在職中の忘年会だった。花形スターとして人気を集め、会場は大盛り上がりだったと語り継がれている。メディヴァ時代にセクシャリティで苦労したことはないそうだ。
理学療法士協会から厚労省に送り込まれ、13年から2年ほどデータヘルスに取り組んだ吉村和也さんは、出向が終わったのを機にメディヴァに加わった。役所時代は関係者へのヒアリングやディスカッションを何度もしたが、多くが自分たちの実績を誇る中で、メディヴァとだけは制度全体をどう活用し、どう発展させていくのかといった大きな議論ができた。他と一線を画していたことから転職先に決めたという。自治体向けに在宅や地域包括ケア、企業向けでは新規事業の開発支援を担当した。職場は大学の研究室の雰囲気で、互いの問題の投げかけが在宅医療制度や地域包括ケアの在り方の議論に発展することもある。日々の仕事の忙しさがさほど感じられない環境だった。
医師兼コンサルタントとしてチームに加わった久富護さんは、「コンサル的に言えば、しっかりとした仮説が立てられた」と話す。面白そうなアイデアがあっても、それが現実離れしていては意味がない。すぐ近くに専門家がいることで議論のスピードが圧倒的に早いのは確かに大きな強みだろう。
久富さんが手がけた案件で印象的なのが、富士フイルムの在宅用ポータブルレントゲンの開発だ。元々のコンサル依頼は別の商品アイデアだった。現場の目線からニーズは低いと感じ、代わりに何が有用かを職場で議論するうちに、在宅医療ではレントゲンが普及していないという課題が飛び出した。在宅患者のレントゲンを撮る必要があると病院まで連れて行かないとならず、関係者に大きな負荷が掛かる。
やぐらのようなものを組むレントゲン撮影装置もあるが、使っている診療所は少なく、撮影にも大変な手間がかかる。久富さん達は製品のアイデア出しから、大きさや重さ、使い勝手などスペックの特定まで手掛けた。開発が進むと桜陳町アーバンがモニターになり、学会のランチョンでは久富さんが医師としてコメントした。その結果、ポータブルレントゲンの商品化に成功した。
連載の第20回で紹介したミャンマーでの乳がん検診普及プロジェクトが生まれたのもここだった。大石さんが海外出張の見聞を話すと「私たちも海外をやりたい」と園田紫乃さん、藤原智子さんの若手二人が手を挙げた。
「どこ」と問われると、すかさず「私達、ミャンマーに行きたいです」との答えが。好奇心から始まったが、ネットを通じて調べるうちに現地の医療に献身的に取り組んでいる岡山大のベテラン医師とのつながりが生まれ、事業化に突き進むのだから面白い。この挑戦が海外チームの設立に結実する。
園田さんは東日本大震災の復興支援では、大石さんらと一緒に取引先にも声を掛けて宮城県気仙沼市で唯一の産婦人科医院の再建を後押しした。津波で機器が流れたので、何が必要かをリストアップしたうえで全国に支援を呼びかけた。暖房・給湯設備を復旧させたほか、妊産婦や乳幼児向けの図書室をつくったところ、全国から本が寄せられるという心温まる体験もした。遠矢院長をはじめ在宅医療部の医師やスタッフも気仙沼の医療関係者に向けて在宅医療のオンライン研修会を開いている。
19年に桜新町アーバンの拡大に併せて朝日生命ビルを引き払う頃には、企業行政チームは一本立ちした組織となっていた。集った面々もそれぞれがメディヴァの経験を通して、自分のやりたいことを見つけた。リーダー役の村田耕平さん(現エムスリー)、医師コンサルタントの神野範子さん(現産業医)、荒木庸輔さん(現新生病院)をはじめとして多くが移籍し、今も残っているのは久富護さん、澤井潤さんら数えるほどになったが、今でも仲は良く、時折飲み会で集まる。ただメディヴァ全体で見ると出戻り組も多く、吉村さんは「私も外で成長していつか戻りたい」と話している。
2000年、メディヴァとプラタナスが足並みをそろえて旗上げした着想は出色だった。医療者とコンサルタントがそれまでに培った知見を活かし、理想の実現を目指して走り出した。その分かりやすい実践の場が朝日生命ビルだったのではないか。それまで接点の乏しかった多様な顔ぶれが集うことでさまざまな化学反応が起きている。
上場を目指すベンチャーは成長へのこだわりが大きいが、ではメディヴァはどうなのか。福祉系ベンチャーに在籍する吉村さんの見立てでは、大石さんも小松さんも前線に出るのが大好きで、会社をがむしゃらに大きくするよりも自分たちがやるべきこと、やりたいことを優先している。何より現場を大事にし、メディヴァの魅力はそこにあるという。組織の活力を保ち続けるには、これからも自由闊達な梁山泊の伝統を絶やしてはならない。