RECRUIT BLOG
2024/05/28/火
寄稿:メディヴァの歴史
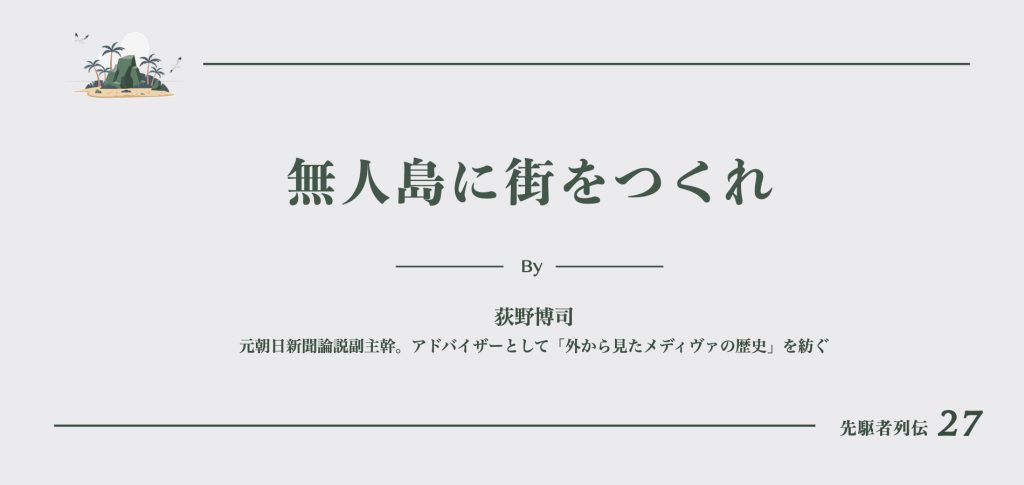
戦後社会を支えてきた団塊の世代がすべて後期高齢者に仲間入りする2025年が目前に迫っている。少子高齢化がすすむなかで、たとえ重い要介護の状態となっても、住み慣れた環境で最期まで自分らしい暮らしを続けるにはどうしたらいいのだろうか。「患者視点での医療改革」を目指して走ってきたメディヴァにとって、地域包括ケアシステムに一丸となって取り組むことは必然だといっては大げさだろうか。
コンサルティング事業部の久富護マネージャーは、地域包括ケアのアドバイス役として飛び回る一方で、現役の医師も務めている。メディヴァに入る前は埼玉県北部にある100床ほどの民間病院にいた。急性期と慢性期の双方の患者を抱えるケアミックスに携わるなかで、患者の希望を叶えるには医療だけでなく地域との連携が必要と感じるようになった。
医大生のころから、コンサルティングにも関心がある変わり種である。NHKスペシャルが取り上げた、外資系コンサルタントが工場内での作業の問題点を洗い出して改善を提案し、収益増につなげる姿に心を揺さぶられたからだ。
二足の草鞋を履くことを決意した久富さんは忙しい診療時間を縫い、2年半ほどかけて医療政策学の修士号を取った。中小企業診断士の資格も得た。臨床をしながらのコンサルティングを目指すなかで出会ったのがメディヴァだった。現在は医師兼コンサルタントとして、週の半分をコンサルティング事業部で、残りを在宅医療を担う医師として働く。臨床医として実体験を積み上げ、患者にどう向き合うのかを考えてきた経歴は強みで、現場で見えた問題点を行政などに示す際の迫力が違う。
地域包括ケアが目指すのは、地域で最期を迎えられる仕組みと久富さんは考える。ともすれば医療と介護にフォーカスが当たりがちだがそれだけにとどまらない。
在宅での医療や介護を受ける高齢者を多くの医師などの専門家が支えたうえ、家族も加えた連携システムを作り上げないとならない。厚労省は「市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げることが必要」としているが、そう言われた自治体の多くは戸惑うに違いない。そこに久富さんたちの出番はある。
例えば、東京・練馬区、葛飾区、町田市、横浜市青葉区などでは自治体が進める地域包括ケア全体の推進役を果たしてきた。こうした基礎自治体は超高齢社会の到来に向けて地域包括ケアシステムを整備する法的な義務が課されている。しかし、それには地域の医師会や病院、診療所、介護事業者など職能団体との調整や市民への啓発も必要となるが、容易ではない。そこでメディヴァが基礎自治体を支援し、地域包括ケアシステム作りを担ってきた。
具体的な業務を挙げるときりがない。全体の推進体制組織の構築と運営、前回も紹介した死亡小票分析での現状把握と需給予測、いざという時の入院先となるバックベッドモデルの推進、多職種(医師、看護師、ケアマネ、訪問看護師、訪問薬剤師)と家族との連携システムの立ち上げと運用、住民や医療関係者向けのセミナーやシンポジウムの企画運営・・・
ともすれば、全国的な話題となっている事業に目を向けがちな相手には、本来必要な取り組みをこちらから示すこともある。首都圏の自治体の一つは、オンライン診療の拡大を委託してきたが、それでなくても医療機関は多く、公共交通機関も整備されている地域だ。そこで在宅医療や看取りの充実策を逆提案し、昨年度は在宅推進のための調査が実現した。さらに区民数千人を対象にした意識調査を実施して分析したうえで、いざという時に入院ベッドが足りない事態にどう対応するかを一緒に考えることにしている。
向かい合う担当者の姿勢も見極めないとならない。大過なく今の仕事を終えたい人ならば、前年度の実績を踏まえて今後の取り組みを粛々と決めていく。並走してやっていく意欲のある担当者であれば、提案に終わらせず、実現の道を一緒に切り開く知恵を出し合う。
目指すのは、自宅でずっと過ごしたいと望んでいるにもかかわらず、老衰やガンでの最期を病院のベッドで迎える人を減らすことだという。患者の希望からも、病院という限られた資源を有効に活用するうえからも、在宅での看取りこそがこれからの主流にならなければならないのだ。高齢者本人にやりたいことをやらせてあげ、家族も思い残すことのない環境を整えることで迎えられるのが、理想の看取りということになる。医師としては痛みなく送り出すことで、それなりに達成してきた実感はあるが、社会全体の仕組みづくりはこれからという面が大きい。
一方、現場での在宅医療の取り組みのなかで気になった点については、学会、論文などを通じて問題点を指摘し、改善策の検討を呼び掛けている。医師兼コンサルタントだからこそできることではないか。
たとえば、胃ろうを選ぶ患者や家族が減っているのではないか、そんな肌感覚から詳しく調べてみた。胃ろうの造設数が最近の12年間でどう推移したかを、厚労省や総務省のデータを突き合わせて解析してみたところ、75歳以上で実際に造設した件数は、2022年が3万6600件で、11年の7万3692件から半減していた。都道府県ごとの人口当たりの件数では最大3.4倍の格差がある事実も分かった。この調査結果はメディヴァのHPで公表している。
胃ろうが必ずしも当たり前でない実態を幅広く知ってもらうとともに、造設手術を選ばないという選択肢もあることを関係者が考える環境を整える試みである。
これに関連して、嚥下栄養についても意欲的な取り組みを始めた。高齢者がご飯を食べられなくなるのは仕方ない、という風潮は、医療現場でもまだまだ残っている。一方で、高齢の患者でも、周囲がしっかり支えれば栄養のあるものを咀嚼し、飲み込み、リハビリなどで筋力がつき、ADL(日常生活動作)のレベルが上がる実態もある。
そこで、患者さんの生活の質を向上させるために専門職同士の連携を促進し、普及させようとしている。咀嚼=歯科医/歯科衛生士、嚥下=言語聴覚士、栄養=管理栄養士、リハビリ=理学療法士/作業療法士といった専門家の共同作業となる。久富さんが名付けた「口腔内連携」を実現するため、医師として働く水海道さくら病院では、まず言語聴覚士と管理栄養士の連携を呼びかけ、この数年でかなりすすんだ手応えを感じている。こちらは7月に学会で発表することにしている。
メディヴァが地域包括ケアシステムつくりを推進し、結果としてアーバンクリニックの開院に至ったのが横浜市青葉区の事業だ。地域包括ケアの構築は、東急電鉄と市が推進する「次世代郊外まちづくり」の一環として進められた。このうち医療介護プロジェクトの事務局を2012年にメディヴァが引き受けた。少子高齢化で鉄道の利用者は間違いなく減る。そうしたときに沿線地域にビジネスの拠点を広げ、新たな事業を展開することで人々がずっと住み続けたい街をつくる「私鉄3.0」という考え方がある。その最先端を走ってきた東急電鉄ならでは取り組みと言える。
地域包括ケアシステム推進部会や在宅医療WGが置かれ、検討作業のなかで今後の死亡者数などの将来予測をしてみた。結果として在宅看取りに対応するには、医療の担い手を3.5倍に増やさないとならないという結論に至ったが、地域の診療所はほとんどが在宅医療をしていない。
この事業に携わってきたコンサルティング事業部の飯塚以和夫シニアマネージャーによると、青葉区は人口の減少が穏やかなので、外来中心の医師会に患者減少への危機感は薄く、自ら在宅医療に踏み出す機運は乏しかった。そこで医師会長に頼まれて開設したのが青葉アーバンクリニックである。今は施設と居宅あわせて500人ほどの患者を診ている。また、メディヴァとして、医師会の在宅医療・介護事業の管理会計作り、給与制度や評価制度作り、グリーフケアの会の立ち上げ支援なども手掛けた。
政策づくりの後押し、地域での実践とメディヴァは幅広く展開してきたが、久富さんはこれからの重要なテーマはインフラ、つまり移動手段や住まいそのものだとする。充実した暮らしには社会との関わりは欠かせない。自宅で医師や看護師に診てもらうだけでなく、地域活動で外に出てきてくれるようになれば患者自身も張りのある暮らしができるだろう。
20年、コロナ禍のなか、経産省の事業として博報堂、ドコモと一緒に「高齢者向けモビリティー」の普及推進事業を手掛けた。そのなかでメディヴァは地域での実証実験を担当した。
調査地域は中山間地(京都・京丹後市、静岡市)、郊外都市(東京・調布市、横浜市)、地方都市(茨城・つくば市)の5か所。55人にモニターとして電動車いすを約1か月実際に使ってもらった。
その結果、当初は「利用を考えたことがある」の回答は33%にとどまっていたのが、実証実験を終えた段階では「今すぐ使いたい、将来使いたい」が78%に達するまでになり、高齢者の新しい移動手段として歓迎されることは確認された。居宅や施設に引きこもらず外に出ることにより、社会参加が促進されるうえ自信にもつながる。また電動車いすに焦点を当てた地域イベントを開催すると期待度も高まった。一人では目立ってしまうが、みんなで乗るというのなら気楽に使えるというのだ。
担当したコンサルティング事業部の目黒ひかりグループリーダーが痛感したのは「電動車いすがあるというだけでなく、地域全体で受け入れられることが大切」ということだ。そのための課題も浮かび上がった。調査の結果、遠くても歩けば30分ほど、2キロ圏内の移動が主だったが、病院などの目的地やバス停や駅などの中継地でいったん降りた場合の駐車スペースという課題がある。地域の理解がないと普及の土壌はできない。
購入すると30万円ほどかかるが、介護保険が適用されれば負担は月に数千円で済む。コロナの影響から、ここ数年の普及は横ばい状態だが、自分で行きたいときに行きたいところにいける個人モビリティーの意義は大きい。ちなみに介護事業部の青木朋美マネージャーのお祖母さんは93歳まで電動車いすを乗りこなしていたそうだ。
地域包括ケアを成功させるためのもう一つの大切な要素である住宅への取り組みについては、稿を改めて紹介しよう。