2025/03/26/水
地域医療の未来に飛び込む、ファーストペンギンたち
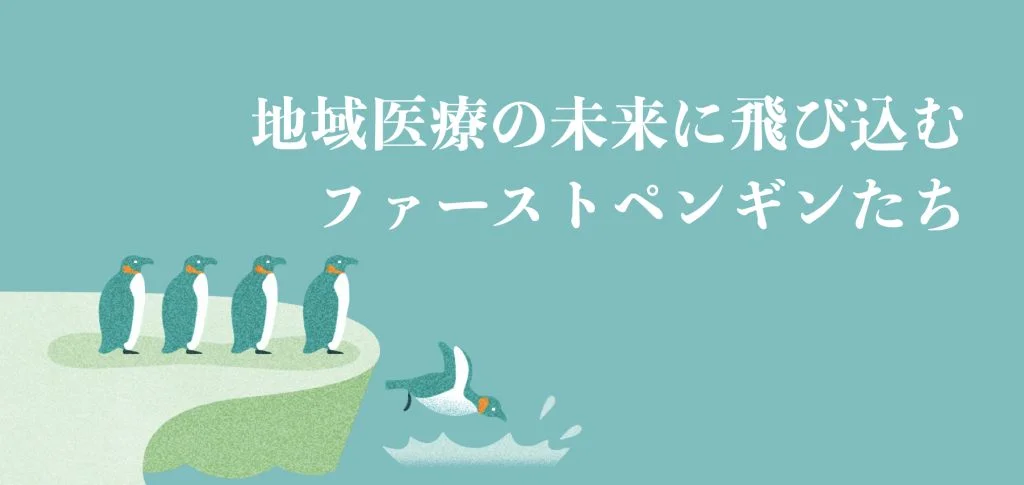
ファーストペンギンとは、群れの中から天敵がいるかもしれない海へ、魚を求めて最初に飛び込むペンギンのこと。時には自らファーストペンギンとなって新しい取り組みを推進し、時にはファーストペンギンのパートナーとして伴走しながら支援する。メディヴァには、そのように地域医療の課題に挑むコンサルタントが多数います。
医療・介護現場での視点、企業・行政支援からの視点、地域の実情やデータに基づいた視点―。
本連載では、様々な視点で地域医療の未来を切り開くメディヴァのコンサルタントに迫ります。
今回は、へき地等に暮らし、医療機関へのアクセスが困難な方に必要な医療を届ける「オンライン診療」への挑戦について。前回に続き医師兼コンサルタントの久富と、弊社代表の大石による対談でお届けします。
内閣府・規制改革推進会議の一員として規制緩和に取り組んできた大石、そして医療現場でオンライン診療を推進してきた久富をはじめとするメディヴァのコンサルタントによる挑戦を、ぜひお楽しみください。
目次
大石:久富さん含めメディヴァで主に自治体向けの支援をしている行政チームでは、へき地等でのオンライン診療の活用を推進されていると思うのですが、どういった課題に対してオンライン診療が有用なのでしょうか?
久富:都市型と言われる忙しい人に向けたオンライン診療とは異なり、へき地等の場合は「医療へのアクセスを阻害されている人に、いかに必要な診療を提供するか」というところがポイントだと思っています。
アクセスは、単純に距離の話もありますが、ご高齢のためADLが低下していて、そもそも医療機関まで行けないという方が多いという面もあるんですよね。例えば慢性疾患の方で定期的な受診が必要な場合、こうしたアクセスの困難さは大きなハードルです。
もちろん訪問診療という手段もあるのですが、やはりへき地等では患者宅まで片道1時間かかるというケースも少なくないため、ある程度病状が落ち着いている慢性期の方については、オンライン診療を取り入れるというのは強い解決策の一つになると考えています。
大石:オンライン診療の領域は以前まで規制が厳しく、私も規制改革推進会議で提言をしてきましたが、近年ようやく規制緩和が進んできましたよね。
久富:2018年に初めて診療報酬でオンライン診療料が新設された時は、対象は再診のみで、3カ月に1度は対面診療が必要、さらには対象疾患も限られていて、算定する医療機関はほとんどなかったのではないでしょうか。
そこから普及し出した最初のきっかけは、やはりコロナ禍だったと思います。当時大石さんが座長を務めていた規制改革推進会議の医療・介護ワーキング・グループでの議論の結果、厚労省より「特例措置」が出され、初診からオンライン診療が認められたんですよね。
大石:当時の論点は、初診から認めるか否か、対象疾患、診療報酬の点数、使用する機器の4点でしたが、最終的にほぼすべての制限が緩和されました。
これは規制改革推進会議での主張ももちろんありましたが、医療界内部からもそれなりに声が上がっていたからこそだと思います。
久富:へき地等にフォーカスすると、2023年度の規制改革推進会議で「オンライン診療を受診できる場所」が拡大した影響も大きかったですね。
我々は「公民館モデル」と呼んでいるのですが、医療法上では週に1,2回、反復性を持って医療を提供する際には医師が常駐しなければならない決まりがありますが、医師不在の公民館でのオンライン診療も認められたんです。
公民館でなら行政職員等のサポートが得られるため、デジタルデバイスに明るくない高齢者も遠方の医師とのやり取りをスムーズに行えます。
もう一点、へき地等では、院長が高齢になって引退され、診療所として「箱」だけが残っているケースも多いのですが、そうした医師非常駐の診療所で、フルオンラインでの診療を行うことも可能になりました。
大石:あとは情報通信機器が整備された巡回車でのDtoPwithN(患者が看護師等といる場合のオンライン診療)も認められましたね。
久富:オンライン診療はプライバシーを確保できる場所で実施するという条件がありますが、その点において車内は最適なんですよね。
ただ医療法上、医療を行える場所は基本的には居宅と医療機関に限定されているため、車内が居宅にあたるかが規制改革推進会議の場でも議論されていたのですよね。
大石:そうですね。患者宅の駐車場に停める場合は「居宅」として、割と早い段階で認められたのですが、争点はご自宅に駐車場がなく、公道等に停めた場合に「居宅」となるかでした。最終的にはそれも認められましたが、こうしてオンライン診療の様々なパターンを想定し、一つひとつ規制を緩和してきて、現状はかなり活用しやすくなってきたのではと思っています。例えばへき地等では、どういった導入事例がありますか?
久富: 2020年頃に新潟県の医療過疎地にある診療所で、オンライン診療を導入した事例があります。地域に2ヵ所しかない診療所のうち1ヵ所の院長がご高齢で勇退を検討され、メディヴァの医療機関チームのグループリーダー中島さんがメイン担当として支援に入りました。
ご高齢とはいえ、しばらくは診療を続けられるということで、週2日は今まで通り対面診療を、その他の日はオンライン診療とし、市内の病院とつなぐDtoPwithNを実施したんです。高齢化が進む地域だったので、大半の患者さんがデジタルデバイスを持っていない状況でしたが、行き慣れた診療所で、いつも通りの診察室で、顔見知りの看護師さんのサポートのもとオンライン診療を受けられるのは、安心感があると思います。
また、オンライン診療の欠点として「採血等の検査ができない」ことがありますが、看護師が患者さんのそばにいることで、そこも解決できます。
全国的にも、医師の偏在や、医師不足の問題は深刻だと思うので、こうしたスタイルで、ある程度の医療の提供が担保できるというのは、非常に良いモデルではないかなと思います。
大石:今後さらにオンライン診療の導入は広がっていくと思いますか?
久富:大石さんや行政チームのグループリーダー大類さん中心に進めていた過疎化が進む茨城県行方市での地域分析でも、在宅医療や介護のインフラが全く足りていない分析結果を踏まえてオンライン診療の活用を提言※されていたと思いますが、へき地等での必要性は、やはり高まっているように思います。
※行方市への支援内容については、以下の記事もぜひご覧ください。
大石佳能子の「ヘルスケアの明日を語る」:羊蹄山麓の「明るい癒着」を目指す「まちづくりフォーラム」
個人的に力を入れていきたいと考えているのは、先ほどお話しした「公民館モデル」や「フルオンラインの診療所」の開設で、今、自治体に働きかけながら実現に向けて進んでいるところです。
ただ、オンライン診療を実施するには県の認可が必要というところと、また診療報酬も対面診療より20%ほど少なく、現状は補助金頼みの事業なので、実施を躊躇する市区町村も多いのではないかなと感じています。そういった意味では、県レベルはもちろん、市区町村レベルでもへき地医療への課題意識というのをより持っていただく必要はあると感じていて、そこに対しても何か私たちで働きかけができるかもしれないかもしれませんよね。
とは言え、やはりオンライン診療に関連する案件は徐々に増えてきている実感はあります。
大石:世の中の流れ的にも、増えてきていますね。
久富:私がメディヴァに入社して取り組みたかったところに「仕組みづくり」があるのですが、へき地等でのオンライン診療の活用はまさしく、そこにつながっているんですよね。オンライン診療の環境を整えるだけではなく、地域のニーズや各診療所の実状に合わせた仕組みを構築していくところから携われていることにやりがいを感じながら、事業を進めているところです。

大石 佳能子(代表取締役/規制改革推進会議委員)
大阪大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクールMBA、マッキンゼー・アンド・カンパニー(日本、米国)のパートナーを経て、メディヴァを設立。医療法人社団プラタナス総事務長。江崎グリコ(株)、 (株)資生堂等の非常勤取締役。一般社団法人 Medical Excellence JAPAN副理事長。規制改革推進会議委員(医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ座長)、厚生労働省「これからの医業経営の在り方に関する検討会」委員等の各委員を歴任。

久富護(医師/マネジャー)
東京都出身。東京慈恵会医科大学医学部卒業、東京医科歯科大学大学院医療政策学修士、社会医学系専門医、中小企業診断士。医師初期研修修了後、民間病院にて内科医として勤務。勤務医時代に医療ビジネスや社会保障に関する研究や活動を通じて、医療・介護領域に対して、多くの課題を感じ、その解決への一翼を担いたいという思いからメディヴァに参画。医師兼コンサルタントとして、臨床現場・サービス利用者・医療政策・経営の4つの視点で医療・介護システムの改善に関与し、その実現を目指している。
コンサルタント・中島
新潟県出身。青山学院大学経済学部卒業。全国に展開する医療法人にて保険請求業務を中心に10年以上の経験をする一方で病院・クリニック及び介護老人保険施設等の新規立ち上げ及び運営に携わる。実務に就きながらサービスを提供する側、される側の様々な想いを体験する。サービス・経営の両面で医療及び介護においても利用する方・スタッフ含め携わる全ての方が笑顔になれる施設の実現を目指す。
コンサルタント・大類
行政・自治体をクライアントとし、主に地方自治体における医療課題調査・医療体制検討や地域包括ケアシステム構築支援、在宅医療・介護連携推進に従事。エビデンスに基づいた客観性・納得性の高い地域課題の見極めと実行可能性の高い施策提案・実行支援を行っている。
目指すのは地域に住まう人の“生活”を中心とした健康で幸福度の高いまちづくり。