RECRUIT BLOG
2023/11/06/月
寄稿:メディヴァの歴史
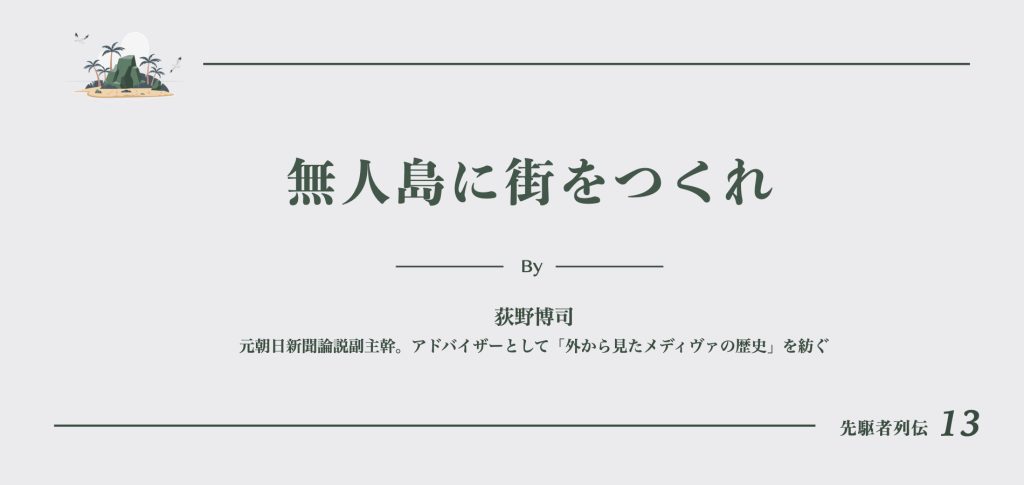
イーク丸の内院の立て直しに乗り出した2007年、もう一つの病院再生事業が始まっていた。こちらは約400床という大きな精神科病院である。
所在地は東京郊外の町田市というが、最寄り駅は京王線南大沢駅とJR横浜線相模原駅。そこから無料送迎バスに乗ること10分、八王子市と接する人里離れた丘陵地のなかを進む。斎場を越し、霊園を越し、ペット墓地を越し、やっと病院があった。
1968年にこの地に井戸の水脈が発見され、翌年に48床の上妻病院が開設された。当初は患者さん思いの医療を徹底して評判がよく、難しい患者を数多く受入れて経営は安定していたと聞いている。しかし、医師の確保が十分にできなくなり、新病棟の建設でつまずいた。経営を牽引していた事務長は退職、さらに看護師の集団退職が相次ぎ、2007年に民事再生に追い込まれた。
引き受け当初に病院を見学しに行った時の印象を大石さんが語る。建設途中で放置された新棟は、コンクリートに鉄筋が刺さったまま錆びていた。旧棟は何故か崖っぷちに建てられて、大きな地震が来たら転がり落ちそうだ。和室の6畳部屋には鉄格子がはまり、半裸のおじいちゃん達が廊下をウロウロしていた。離れたところに建てられた事務棟の地下にはいつからあるのか分からない家具や物品が詰め込まれて、心霊スポットという噂もあった。
悪評が積み重なり、経営的にも厳しい精神科病院である。だが、このまま閉めてしまってもいいのか。現に長期にわたって入院している人々がいる。東京都内で行き先の無い患者を多く引き受けていた現実もあった。
病院の再生では異例だが、何とか閉じないで欲しいという意向が東京都から関係者に伝えられたとも聞く。ようやく再建スポンサーとしてファンドが手を挙げたが、お金は出せても経営力には限界がある。運営をメディヴァが引き受けることになった。ここは当初から経営を預かる小松大介取締役の説明を聞こう。今も毎週1度は用賀から1時間半をかけて病院に通っている。
「創業7年のメディヴァは医療コンサルではまだまだ新参者。病院建設や医療機器の調達などにコンサルが付くのは医療業界では一般的で、ビジネスとしてのうま味も大きい。でも私たちが無理してやる必要はない。そうしたなかで、当時ほとんど手付かずの分野が病院再生。社会的な意義がある民間病院の立て直しに取り組んだ」
確かに無人島によそでは見たことのない街をつくろうという挑戦である。ライバルが少ないのは確かだが、本当にメディヴァにできるのか。クリニック経営や、病院コンサルの実績はあったが、これだけの規模の病院再生は未知の世界である。そのうえ再生案件の場合、儲かっていない病院からいきなり大きなフィーを頂くことはできない。最初は業務の立て直しに専念し、報酬を受け取るのは後回しになる。
病院の状況を踏まえると大きなハンデを背負ってのスタートである。財務面の行き詰まりが倒産の直接のきっかけだったが、それまでに院内での過度の拘束や暴力沙汰がメディアで報じられている。当時の悪評は今もネットに残っているほどだ。
当時、新聞記者だった筆者も「やめた方がいい」と大石さんに話した記憶がある。日本の精神科医療の問題点は度々指摘されている。世界の主要国の中で人口当たりの病床数が飛びぬけて高く、入院患者が多い。そして長期入院や身体の拘束など患者の人権が守られていないと批判される事例も少なくない。理想の医療を目指して颯爽とデビューしたメディヴァが抱え込むには、あまりにも冒険だからだ。
それでも突き進んだ。難しいほど取り組む意義があるし、なにより患者が路頭に迷ったら大変だ。「医療界における『革新』と新しい『価値創造』に取り組む」というメディヴァのDNAが敢えて困難な道を選ばせたのだろう。
予想されていたが、再生までの道のりは平坦では無かった。
院内で保管している薬を盗み出す男性看護師がいた。自らが起こした傷害事件を隠したまま看護助手として働いているスタッフもいた。その度に敢えて警察に連絡し、時には当人が院内で逮捕されることで、今後一切このようなことは許さないという経営側の毅然とした姿勢を示すよう心掛けた。
これに精神科病院ならではの苦労も加わる。院内で自殺を試みる患者さんが出たときには、小松さんは台風の中、車を飛ばして現場に駆け付けた。入院患者が外出から戻らないと、病院スタッフやメディヴァが派遣している事務長らが総出で捜索である。患者間の喧嘩騒ぎに加え、看護師が親しげに患者を叩く場面も目にした。長い間の顔見知りという親密さからとはいえ医療機関では許されない行為で、厳重に対応する。気が休まらない日々だった。
問題のあるスタッフにはお引取りいただき、新人を補充しながら院内の教育や研修、指導体制を強化していった。人事評価制度も整え、どういう行動が求められているかをスタッフに示す。接遇を改善するよう心掛け、プロパーの栄養部とのコミュニケーションを深めて食事をより美味しくし、敷地内にある桜の古木の花見、盆踊りや流しそうめんと入院患者が喜んで参加してくれる催しにも力を入れた。目安箱を設置して患者の声に耳を傾け、思いついた改善策はなんでも取り組んだ。
体に合併症を抱えている患者のために内科医も確保した。内科やリハビリ疾患を抱えた高齢の患者は少なくない。一方では統合失調症への薬物療法が劇的に進んだ。精神科病院の役割が変わりつつある。
支援開始から10年後に懸案だった新棟の建設にとりかかった。過去の「黒歴史」を物語る畳敷き、鉄格子の古びた病棟を壊し、跡地に完成した新棟は6階建て。急性期や亜急性期の患者が入る閉鎖病棟、体にも合併症を持つ患者向け開放病棟などのほか、作業療法室、また精神科病院には珍しい身体のリハビリを実施する理学療法室も作った。運動機能の低下や体を動かさないことによる廃用症候群や骨折後の回復のための取り組みだ。
救急患者の3割は精神的な症状も伴うといわれる。例えば意識が混濁し幻覚や錯覚が見られる「せん妄」だ。それが残っていると一般病院では救急科から一般病棟に移せない。こうした人を受け入れることも心がけた。近年では、行政や近隣の病院からの紹介先になり、よそでは対応出来ない患者を一手に診ることになった。地域の困りごとを解決し、病院収益にも繋げることが出来た。
こうして地域における「ここホピ」の存在感が高まるにつれ、当初は見向きもしてくれなかった大学医局も医師を送ってくれるように。途中、理事長や院長は交代し、当初の非常勤中心で常勤医は4人という貧弱な体制を最終的に常勤医11人まで増やした。
病院は患者を押し込めて隔離する場ではない。どう在院期間を縮め、社会復帰につなげるか。平均の在院日数は、2012年の700日がコロナ期に入ったばかりの20年には300日に短縮した。ただ、病気を抱えて長い間、病院暮らしだった人が地域に戻るのは容易ではない。まず、在宅医療が欠かせないことから、訪問看護ステーションを設け、当面の暮らしができる住まいを大家と交渉して用意できた。退院後のワンクッションという位置づけで、社会での暮らしになじめば別のところに移っていくことになる。
多くの人々の懸念を背に取り組んだ「ここホピ」は、年間損失7000万円という万年赤字から劇的な改善を遂げ、メディヴァの支援先の中では内容も数字も優等生である。日本の精神科医療に厳しい目を向ける方々から合格点をもらうのは容易ではないが、16年間の試行錯誤のなかで目指す姿が見えつつある。
「ここホピ」が、日々の暮らしで傷つき心を病んだ人々が静かに療養できる場として充実させなければならない。いまもメディヴァの真価が試されている。