RECRUIT BLOG
2025/02/25/火
寄稿:メディヴァの歴史
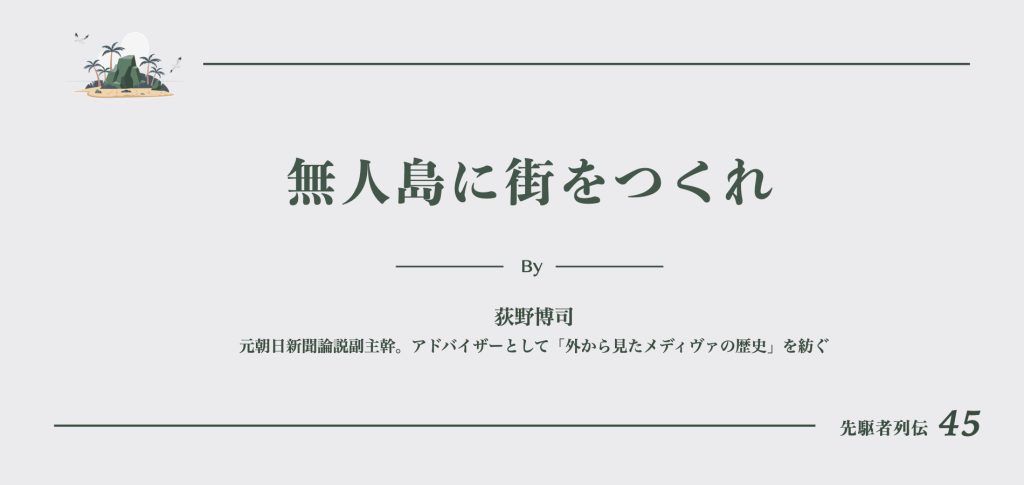
同善会クリニックを訪ねると、理学療法士らの指導のもと受診者が黙々と体を動かしているリハビリ室、外来患者で埋まった待合スペースや診察室の先に、にぎやかな声が聞こえてくる一室があった。医療法人社団同善会が地域に開いている交流スペース「みのるーむ」である。
訪ねた日は健康麻雀が開かれていた。最初のうちは卓を囲む4人のほかは2人が観戦するだけだったが、その後、一人二人と姿を見せて1時間後には10人ほどになった。ルールの習得や牌さばきはこれからという初心者の女性も混じり、ときおり手から牌をこぼしながらも楽しそうにゲームに興じている。
医療施設などの娯楽室でのゲームといえば将棋や囲碁が連想されるが、こうした2人だけの対面競技では雑談しながらとはいかない。みのるーむの麻雀ではプレー中も冗談が飛び出し、補聴器の最新情報が取り交わされていた。参加しているのはかかりつけの外来患者が中心だが、受診したことのないご近所さんも交じる。町内会のチラシなどで案内をするうちに集まってくれるようになったそうで、ときには職員の付き添いで同善病院の入院患者が顔を出すことさえある。
交流の場を切り盛りしていたのは、地域コーディネーターの田辺智美さんだ。院内外の連携・地域活動を担うコミュニティ支援室の一員である。メンバーが足りないときの代打ちも務めながら、参加者との会話を心掛けている。単なる親睦だけでなく、医療機関として患者の経過観察の側面も持つという。
足を運ぶのは住民だけではない。地域の社会福祉協議会や包括支援センターの方々も訪れる地域資源の一つになっている。南千住東部包括支援センターの支援コーディネーター田村悠二さんによると、「当初、麻雀は賭博の一つという印象もあり、行政は一歩引いていた」そうだ。しかし、4人が向き合うことでコミュニケーションが深まることから「高齢者の交流にはふさわしいと受け止めるようになった。医療関係者ら専門家がすぐ近くにいる『みのるーむ』は大変心強い場所だ」と評価していた。
この部屋は、元は住民サポートセンターだった。医療機関の相談所というのでは敷居が高いことから、23年7月に住民と同善会の人々がともに活動する拠点に衣替えした。楽しむのは麻雀だけではない。医師やスタッフ、患者が店主になるみのるーむ喫茶、アートコミュニケーターらとの対話を楽しむアート喫茶、昭和歌謡の会、健康体操、栄養教室、将棋教室など毎週火曜と木曜を中心に多彩な企画が用意され、それぞれに常連が生まれている。棒を投げて標的を倒す、フィンランド生まれの競技モルックの日もあった。
ほかにも年に数回、クリニックのリハビリ室や駐車場、前庭を開放して「あおぞらカフェ」を開いている。当初は医師による健康講座が中心だったが、これでは医療や健康に関心の高い住民しかやってこない。そこで様々な人が楽しめるイベント形式を採り入れ、幅広い層に集まってもらうように工夫した。
患者さん、元患者さん、地域住民、医療福祉関係者といった多彩な顔ぶれが「久しぶり!」と気軽に会い、一緒にイベントを楽しむ。医療者と患者ではなく、人と人として交流する場になっている。地域とのつながりを深めることは、病気にかかっている人だけでなく、健康状態が気になる人、さらには医療機関を敬遠してきた人へのアクセスの道を開くことにつながる。
患者の健康には、貧困や孤立、孤独など、健康問題を引き起したり、治療の妨げとなったりしかねない社会的課題が関わることも少なくない。「健康問題に関する社会的課題を解決しうる非医療的な社会資源につなげ、ケアの機会を患者とともにつくる活動」と定義される社会的処方の視点や、治療だけではなく個人のやりがいや生きがいに目を向ける姿勢は、コミュニティホスピタルとして患者の人生をみる医療を実践する上で不可欠だろう。
CCH(コミュニティ&コミュニティホスピタル)協会でコミュニティプランナーを務める福井彩香さん、コミュニティナースの小笠原彩花さんの「あやか」コンビは地域とのつながりを深め、医療が地域と連携して暮らしを支える仕組みを整えることに知恵を絞っている。
最近の取り組みの一つを紹介しよう。先ほど紹介したみのるーむ、あおぞらカフェを活用した事例である。
飲酒量がやや多く昼夜逆転生活になりがちな外来患者さんがおられた。みのるーむ喫茶で開かれた麻雀教室での雑談から、以前は三味線演奏者でボランティアでの演奏が生き甲斐だったが、コロナ禍以降は機会がないことがわかった。そこで、院内スタッフと共に、あおぞらカフェや病棟での演奏会の機会を設けることにした。その準備のために、みのるーむでお話しする機会を意図的に増やしたこともあり、外出の機会が増えて飲酒量も減少し、生活リズムにも改善傾向がみられたという。
地域とのつながりを保ち、やりがいを提供するのは、社会的処方の一つといえるだろう。コミュニティ活動は在宅や外来、入院といった医療の脇役ではなく、ともに医療を支える重要な柱と考えたい。これまで分離しがちだった医療と街の融合を目指し、体と心の健康に欠かせない人との関わりの交点づくりともいえる。
コミュニティ支援室の活動を支えるため、在宅医療、入院、外来の各センターには10人ほどのコアメンバーがいて、リーダーも決めている。そうした人々が定期的にコアメンバー会議に参加し、コミュニティ活動などについて論議している。いま「すべての人に、あなたらしい人生を」という理念のもと地域活動ビジョンを策定中だ。
地域に開かれた病院として、住民の予防医療にも力を入れ、地域の包括ケアシステムの中核を担うパイロットサイトとなった同善会で蓄積した成果は、一つ一つが全国での展開を目指しているCCH事業の先行例となっていく。
ただ、地域とのつながりを深め、持続させるには人件費などの経費をどう賄うのかをしっかりと考える必要がある。今の医療保険制度では点数につながらないため、余力に乏しい中小病院では二の足を踏むことになりかねない。一方、社会的処方の重要性が認識されるなかで挑戦しなければ、少子高齢化時代の競争には勝てないのも確かだ。
同善会とCCH事業の法人事務局長を兼務している草野康弘さんは、コミュニティ事業を通じた人材の採用や教育面での効用にとどまらず、政府が進める重層的支援体制整備事業に着目している。
この整備事業は5年前の社会福祉法の改正で生まれ、地域共生社会づくりに向けて市町村での支援体制を整備することを掲げている。そこには相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に進めるための交付金の制度もある。こうした資金を取り込められたら、さらに安定した活動につながることが期待できる。
「治し、支える医療」が経営にもプラスになれば、医療者自身の意識も大きく変わるだろう。地域に帰ってやりたいことを実践したいという医師は一定数いる。退院させた後の患者に関わりたい医師も少なくない。そうした人々を呼び寄せる効果が見込まれる。
同善会での試行錯誤を通じて得られた知見がCCH事業を通じて全国の中小病院に広がり、地域の医療が変わることを期待したい。