RECRUIT BLOG
2025/02/13/木
寄稿:メディヴァの歴史
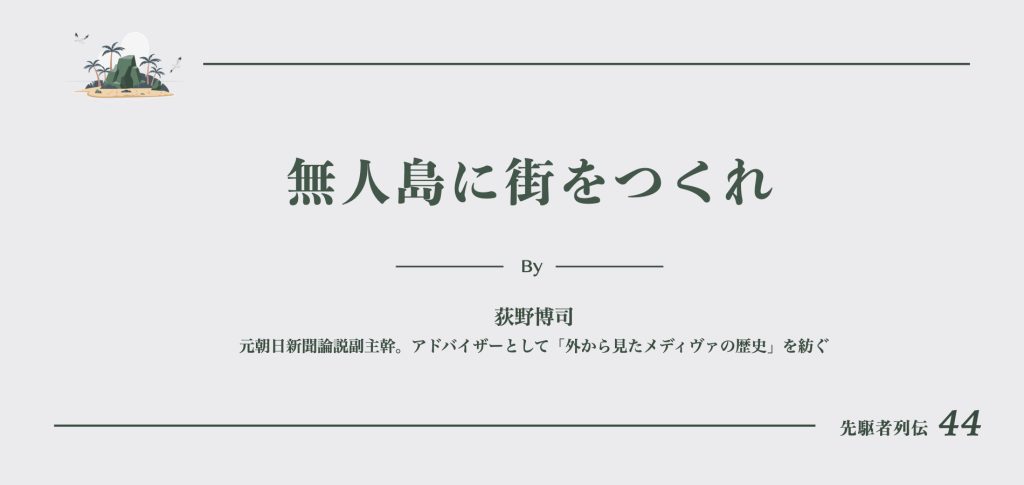
新たな時代の医療像を追い求めながら25年間にわたって活動を続けてきたメディヴァには、パイロットサイトを持つコンサルティング会社という特色がある。
IT技術が急速に進むなか、過去のデータや統計数値を文章やグラフに仕立て直しただけの提案書など、生成AIの方が上手に作る時代を迎えようとしている。それだけに医療の現場に理想を投影し、実際に体を動かして医師らとともに目標を目指す姿勢が一段と求められる。メディヴァにとっての貴重な実践の場が東京・台東区にある医療法人社団同善会だ。
今も残る都電の終着、三ノ輪橋駅から歩いて5分、今年の大河ドラマの舞台として脚光を浴びる「吉原」からは15分ほど。近隣には簡易宿泊所が集まりドヤ街と呼ばれた山谷地区もあれば、新築のタワーマンションがそびえる南千住もある。同善病院(45床)と同善会クリニックは、長い歴史を持ち多彩な人々が住む下町に根を張っている。
ルーツは明治中期の尋常小学校にまで遡る。その後、夜間学校や保育園の経営に転じ、東京大空襲では焼失を免れた建物に戦災者を収容した。戦後の助産所を経て1956年から病院運営に乗り出し、2007年にはクリニックも開院した。教育から医療へと大きく舵を切った法人である。保育園舎を転用したクリニックは階段がなだらかで一段ごとの高さが小さく、手すりの位置も低い。子供たちが過ごしていた名残がいまも随所に残っている。
法人の承継先を探していたオーナー医師からメディヴァが運営を引き受けたのは2015年6月のこと。以前に紹介した水海道さくら病院やこころのホスピタル町田と同じように、自ら運営にあたっている。今ここではメディヴァとシーズ・ワンが推進しているコミュニティ&コミュニティホスピタル(CCH)事業のモデル病院として、意欲的な取り組みが進んでいる。
中小病院が地域包括ケアの中核的な担い手になれば、地域社会の中で輝く存在になって経営的に安定するし、住民の健康や暮らしも支えられる。そんな「治し、支える医療」の普及を目指すのがCCHだ。
歩いて1、2分の距離にある病院とクリニックは一体で運用され、機能強化型在宅療養支援病院(単独型)に認定された病院には24時間、365日の在宅医療や訪問リハビリにあたる在宅医療センター、回復期のリハビリや在宅患者の一時受け入れ(レスパイト入院)などを担う入院センターが置かれている。クリニックは、かかりつけ医の機能を持つ外来センターである。以前は外来と病棟だけだったが、CCHを目指して2022年4月から在宅医療に乗り出した経緯がある。
ワンストップの総合診療(健康づくり)、地域医療人材の育成(人づくり)、地域包括ケア(まちづくり)の三つを同時に追い求めるという欲張りな目標を掲げる同善会の司令塔がコミュニティ支援室だ。
外来・在宅医療・入院・地域活動を継ぎ目なく繋ぐ役割を果たすため、23年11月にそれまでの退院支援室から衣替えした。各部門の代表によるミーティングで連携や情報の共有にあたるだけでなく、周辺の医療機関や介護施設とのネットワークを築き、さらに地域の人々と取り組む活動の支援にもあたっている。
支援室長の小笠原雅彦副院長は、同善、水海道さくら両院の在宅医療センター長も兼務する多忙の日々を過ごしている。名古屋出身で、32歳で重い腰を上げて愛知県外に出てきた、と経歴を語っている。大学病院時代と比べて、患者の暮らしにも向き合うコミュニティホスピタルでは発想が変わってくることを自覚したという。
例えば、看取りの際に以前は「どうやったら死期を遅らせられるか」を考えていたのが、「残された時間でどんなことができるのか」「この人はどこまで生きていたいのか」を真剣に考えるようになった、とCCHを紹介するホームページで振り返っている。病室に行っても患者と何をしゃべればいいのかわからなかったが、在宅の現場に出たことで自宅に飾られた写真や賞状などが目に入り、おのずと話が続くようになったともいう。
地域医療の担い手に求められるのは、単に患者の病気を治すのでなく、日ごろからの予防や退院後のケアも含まれ、患者という一人の人格に向かい合う姿勢だ。しかし、立派な理念を語ったところで肝心の人材が育たなければ広がらない。
同善会には自らが実践するだけでなく、そうした志をもった医師を増やすという使命がある。23年度からCCH総診プログラムを立ち上げ、在宅医療の先駆けである桜新町アーバンクリニックなどとの連携で、総合診療医の育成に乗り出している。
専門医を育てる仕組みとしては、大学病院の診療科ごとに置かれた医局がよく知られ、教授を頂点としたピラミッド型の構造が一般的だった。総合診療医の教育フィールドは従来、高度急性期機能をもつ大規模病院と診療所に限られていた。そこにコミュニティホスピタルを軸に据えた育成プログラムという新たな選択肢を提示したのがCCH総診だ。医局でない医局、地域に開かれた医局といったところか。
現在、CCH総診では15名の指導医のもと、5名の専攻医が研鑽を積んでいる。専攻医は提携先の医療センターや大病院、外来クリニックなどを回り、3年目を同善会で迎えるといったローテーションで総合診療医に求められる幅広い知識や体験を積む。単に医療だけでなく、地域での無料診療、生活相談、さらには生活困窮者への炊き出しなどにも参加する。同善会は医療を受ける機会さえ乏しい人々が住む地域も抱えるだけに、社会が抱える問題を体験する重要な機会となるのは確かだ。
3年間のプログラムを受けた医師の一人は「急性期から慢性期まで幅広い疾患・症例を経験することでスタンダート以上の総合診療医になれる」と語っている。
政府が推進している地域包括ケアシステム構想では、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される社会の実現を目指している。その中軸を担うのが、かかりつけ医として患者の暮らしや地域社会にも目配りできる総合診療医である。
ただ、総合診療医は2018年に加えられた19番目の専門医カテゴリーである。新参の領域で規模も小さいし希望する医師も限られている。こうした状況を変えるうえでも優秀な医師を育てることは急務だ。
CCHという挑戦的なビジョンを掲げての同善会の大転換は、それまでの病院勤務になじんでいた人々の間に不安や警戒感も呼び起こしたようだ。新路線を打ち出した2022年4月以降で3分の1ほどの職員が方針の違いなどを理由に退職した苦い経験もしている。
一方で新たな挑戦が意欲ある人材を呼び集める効果をもたらした。同善会とCCH事業の法人事務局長を兼務している草野康弘さんによれば、理念に共感して自ら入職を申し込んでくる人が増えている。医療分野は流動性が極めて高く、人材不足は病院経営に付きまとう悩みである。人材斡旋業者に紹介料として年収の20-30%を払って要員を確保する医療機関は少なくない。そうしたなかでCCHや総合診療医に関心をもつ医師をこの2年間で10人も採用できた実績は草野さんにとっての誇りだ。
今、本当に必要とされるのは、「病気」を診る医療ではなく、「患者」を診て、「社会」を診て、「治し、支える医療」への大胆な転換である。同善会の取り組みは、経営が厳しさを増している全国の中小病院が再生する道筋を示している。
CCHにはもう一つの重要な柱がある。病院やクリニックから飛び出し地域に向き合うコミュニティ活動については、次回に紹介しよう。
(つづく)