RECRUIT BLOG
2025/01/10/金
寄稿:メディヴァの歴史
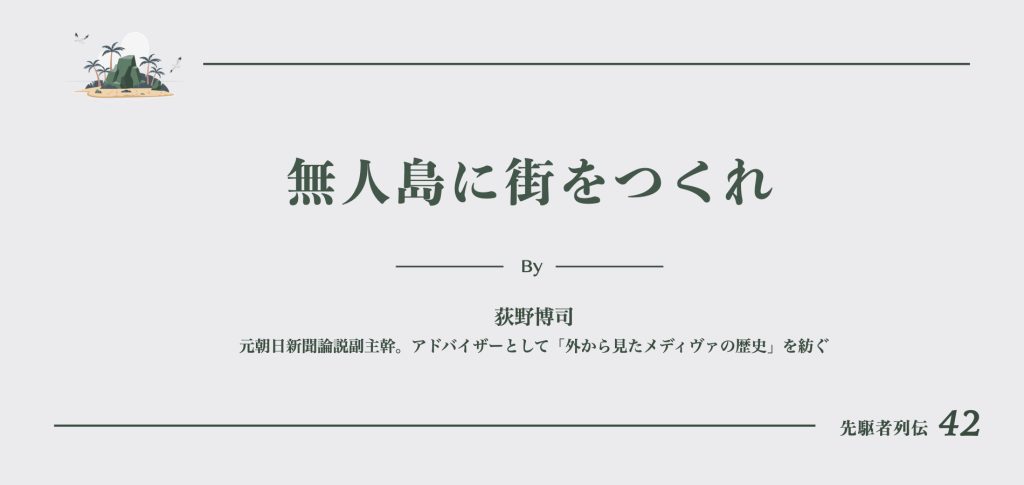
「無人島」に生まれた新たな街を訪れたら、心がほっこりとした。福岡支店がある博多駅から地下鉄で10分ほど、中央体育館や中央図書館などの一角に海外からも見学者がやってくる福岡市認知症フレンドリーセンターがある。ここでは運営を委託されたメディヴァの社員5人が忙しく働いている。
認知症になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるまちを。福岡市が掲げる「認知症フレンドリーシティ・プロジェクト」の拠点施設として、2023年9月にオープンした。
施設そのものが認知症に寄り添うショールームとなっている。すぐに気が付くのは、認知症の人が使いやすいように工夫された内装だ。グループリーダーの木内大介さんが中心となって開発した環境デザインをもとに、クリーム色やこげ茶、緑などではっきりと塗り分けられている。以前に紹介した水海道さくら病院と似たたたずまいだ。
センターに期待されている役割はいくつもある。まず情報発信の拠点として、認知症当事者や家族、職場などからの相談を受けて助言をする。そのためにゆったりとした相談スペースが用意されている。
認知症への理解を深めてもらうためにさまざまな集いも企画している。この12月には、認知症サポーター養成講座、快適空間づくり勉強会に加えて、9月から続いていた「だいたいおっけー展」を振り返るトークイベントも開催した。
何とも変わった名称の展示会では、認知症当事者88人の語りをもとに、大学生たちがそこから感じ取ったことをもとに制作した作品が並べられた。若い世代にとって認知症は「暗くて悲しい」イメージしかなかった。しかし、当事者の話を聞くうちに自分のできることに折り合いをつけながら過ごしていることが分かったという。
展示作品の一つ「そうなんでスタンプ」のコーナーには様々なハンコが並んでいる。認知症当事者が教えてくれた暮らしの工夫がスタンプになっており、来館者は自由に押すことができる。たとえば、こんな文面だ。
―初対面なのかそうじゃないのか分からないから、「はじめまして」は使わない。「こんにちはお久しぶり!」って挨拶したら、だいたい相手もその気になるでしょ。
―家中のモノをそれぞれ定位置に戻すのは、もうムリ!大事なものは全部ひとつのところに集めて「とりあえずここに戻す!」コーナーを作っている。
ほかの展示にも考えさせられた。間違って同じものを買ってしまった時のアイデアをまとめた「2個あるんです掲示板」「あらたな料理のさしすせそ」。前向きに生きる姿勢を伝えようとする学生の熱意が伝わってくる。昨年12月18日で終わる予定だったが、好評なことから会期を1月10日まで延長し、福岡市科学館での巡回展示まで決まっている。
「だいたいおっけー」。なかなか含蓄のある言葉である。
家族や医療機関、行政向けの勉強会や研修では認知症体験のARグラスが大活躍している。発症すると視野や距離感が全く変わってしまうことがあり、移動が怖くなることが実体験できる。視察に訪れた福岡市内の病院関係者は「実際の医療現場でできる声のかけ方や接し方、環境をどう整えるべきかを考え直す」と病院サイトに感想を書いていた。
また、認知症当事者に使いやすい製品などの展示も興味をひく。連載28回で紹介した「誰もが安心してずっと使えるガスコンロ」の実物があった。メディヴァがリンナイや西部ガス、福岡市と手を組み、認知症の方たちにも開発プロセスに加ってもらった自信作である。
操作手順を間違えたり、一定時間放置したりしていると自動的に火が消えるほか、表示の文字サイズや配色を見やすくするなどの工夫には、認知症になっても料理を諦めないでほしいという思いが込められている。音声による警告装置も内蔵するが、「点火します」ではなく「火をつけます」と分かりやすい表現にしたうえ、冷たい印象を与えがちな合成音声でなく声優の生の声を72パターンほど入れた。
認知症当事者や職場体験に来ている中学生が参加して料理に取り組むイベントが開かれたが、これはガスコンロをさらに改良するための実証実験も兼ねている。また、腰の部分にワイヤが入り、結ばなくても使えるガーデニングエプロンは、以前のようには手先が利かなくなった人たちに喜ばれているそうだ。
このセンターでは認知症の人も貴重な戦力である。週1回2時間ほどの勤務だが、5人が在籍し、データ入力、案内、掃除などできることをやってもらっている。受付にある分身ロボットを通じて、当事者が遠隔案内をする様子は地元ニュースなどで大きく取り上げられた。時給は1000円ほどだが、当事者にとって居場所があることで元気になる効用は大きい。これまで奥さんから離れようとしなかった70歳代の男性が、今は写真撮影を率先してやってくれているそうだ。
こうした評判は海外にも広がる。10月にはフランスのレユニオン島から、介護士養成の専門家が来館した。フランス発祥の認知症ケアの技法で「人間らしさを取り戻す」ことに主眼を置くユマニチュードを学ぶなかでセンターを知り、はるばる視察に来たそうだ。当事者との円滑なコミュニケーションを重んじるのがユマニチュードだが、AR体験は衝撃的だったようだ。参加者は「『環境による混乱』があることは、文献や書籍を読むことでも理解は出来ますが、身をもって体感するという体験に勝るものはありません」というコメントを残している。
認知症デザインが注目され、地元のデザイン協会に紹介されてやってくる海外の視察者も増えている。センターに備えられた訪問ノートには、英語だけでなくハングルや中国語、タイ語などの書き込みも目につく。
訪れる人々の案内役や講演会の講師などに忙しい党一浩センター長は、もとは自動車の整備士だった。親のケアを機に転身し、30年にわたり施設から在宅まで幅広く介護を経験してきた。当事者の望む暮らしを実現させる近道を考えたとき、地域や社会の認知症に対する理解こそ欠かせないとして、これまでの経験を生かすべく、福岡市のプロジェクトに手を上げた。
運営は医療・介護に実績のあるメディヴァに委託するという話から、福岡支店を率いる柿木哲也さんや木内さんとつながり、23年7月にメディヴァに加わった。オープンを2週間後に控えた9月1日に井上知美さん、上田智美さん、安藤由紀子さんが加わり、24年9月には牧之瀬潤さんが若年性認知症の担当者として配属された。みんな九州人だ。
鹿児島の出身の牧之瀬さんは、福岡で広告代理店や広告制作会社勤めを6、7年やった後、社会福祉士の道を選んだ。現在では、若年性認知症コーディネーターとして、市内の認知症疾患医療センターや関連機関からの依頼を受けて対応している。
牧之瀬さんによれば、働き盛りでの発症だけに就労支援が一つのポイントになる。進行度次第だが、企業にもメリットはあると力説している。障がい者雇用の実績になるうえ、部署の意識改革のきっかけにでき、業務の見直しにもつながるからだ。現在は5、6件の案件を抱えている。「受診、相談に来てほしい。早期発見できないと、できることが狭められる」と語る。
それまで訪問看護師や病棟看護師をしていた井上さんは、産業保健師に関心があり、メディヴァを志望した。最初は「会ったこともない人についての相談にどう答えたらいいのか」と戸惑い、同僚で精神保健福祉士の上田さんから多くを学んだと振り返る。
福岡市やセンターの活動には、大企業も目を向けるようになってきたようだ。ガスコンロを開発したリンナイにとどまらず、最近ではトヨタが認知症当事者の自由な移動の支援に乗り出した。免許返納者のなかには当事者も含まれている。そうした人の移動を応援しようというのだ。
装着してもらうスマートウォッチに目的地への方向などを表示するナビアプリ「ツギココ」を入れ、一人で移動してもらう実証実験を重ねている。「もう一度大宰府天満宮に行きたい」という方がヘルパーの介助なしで、西鉄電車を使って大宰府に行き、参拝したのちに名物の梅が枝餅を食べてきた。たしかに自動車メーカーのトヨタは移動の会社とも言える。高齢化社会で新たな分野を開こうとしているのだろう。
1年2か月ほどで来館者は1万人を突破した。市役所も党センター長自身も、「1年間で1000人も来たら上出来」と考えていただけに、社会の関心の高さに驚かされた。福岡市はセンターの実践例をふんだんに盛り込んだ認知症デザインの手引きをつくり、それをもとに地下鉄の駅や区役所など60施設にデザインを導入した。福岡市の「認知症の人にもやさしいデザイン」は24年度のグッドデザイン賞ベスト100にも選ばれたほどだ。
いま党さんは「社会が変わっていることを知ってほしい」という。「認知症の人と話してみたい」と話す自治体の人がいるが、実は身の回りに多くの患者がいるのに気が付いていない。当事者がカミングアウトできないまま、引きこもってしまう社会を変える一歩としてセンターはあると考えているからだ。
25年にわたるメディヴァ・プラタナスの活動のなかで蓄積された知見と意欲ある人材が詰まった施設といえるだろう。センター発で次はどんな情報が届くのか。楽しみである。