RECRUIT BLOG
2024/12/18/水
寄稿:メディヴァの歴史
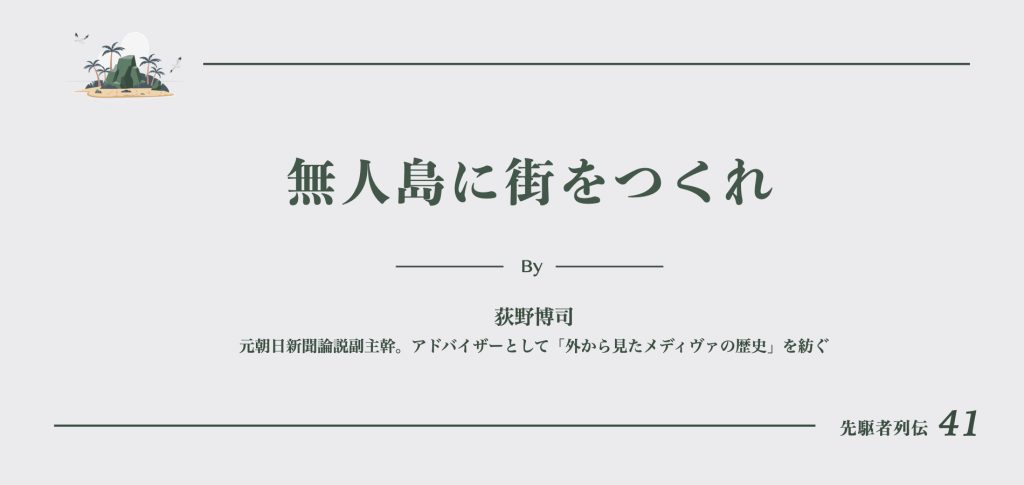
東京・世田谷で生まれ、四半世紀の間に首都圏に多くの拠点を築いてきたメディヴァが、遠く離れた九州に支店を設けたのは5年前のことである。海外からの訪問客が増え、膨張を続ける国際都市・福岡に目を奪われがちだが、九州の多くの地域では高齢化や人口減少が続いて医療経営は厳しさを増す一方だ。地域の医療システムを守るための仕事の依頼が次々と舞い込んでいる。
支店があるのは、博多駅から歩いて5分ほどのビルの6階。10人ほどが入ればいっぱいのオフィスだが、週なかばのお昼時に伺うとほとんどが空席だった。多くのメンバーが在宅勤務だったり、現場に出向いていたりしているからだ。ここで総勢20人の「西日本の砦」を率いているのは執行役員で九州エリア統括支店長の柿木哲也さんだ。
支店が開設されたのは2019年7月だが、当初は常勤者がいなかった。すでに福岡出身の入川文さんが九州要員として入社していたが、1年間は東京勤務で仕事を学んでいたからだ。20年初め、コロナの感染爆発が迫るなかで福岡に戻り、本格的な支店業務に取り組むようになった。
最初は博多駅の横にあるビルのシェアオフィスだったが、席が2つしかなくてあまりにも手狭だ。4席の部屋に移ったものの出張者が来るとすぐに満杯になるので、今の場所に移った。25年2月には耐震性の高い新オフィスに移ることになっている。相次ぐ引っ越しは、そのまま支店の拡大の足取りを物語っている。長らく九州支店を名乗っていたが、昨年から福岡支店となった。北九州支店の設置に伴う変更である。
柿木さんの入社は2008年。最初に抱えたのが福岡の案件だった縁もあり、その後も九州での仕事が多かった。営業所が置かれた時期もあったが、常勤者がいないために2年もしないで閉じたことがある。このため柿木さんはほぼ毎週東京から出張して九州を回っていたが、これでは仕事が捗らない。そこで西日本を束ねる支店が新設されることになった。コロナ禍が広がって長距離の移動がきわめて難しくなった事情もあり、福岡に定住することになったという。
西日本の拠点というのなら大阪辺りが定番のように思われがちだ。九州では東京から離れすぎていないか。そんな疑問への柿木さんや入川さんの説明は明快だった。
西日本には民間の医療法人が多くて「西高東低」といわれるほどだが、医療コンサルの世界でも京阪神には老舗が根を張っている。内容的には負けていないとしても、長年の関係性は崩しにくい。それに比べると九州は手薄な地域が多く、病院の事務長経験者が始めた事務所のほか医事レセプト業務、資材納入などを手掛けている会社や病院経営に関係する法人が、業務の一部として手掛けている程度だった。これでは本当のコンサルティングは難しく、メディヴァが活躍する余地は大きい。
生粋の九州人である入川さんによれば、「医療機関はハコこそそろっているが、通ってくる患者も、働く医療関係者も減っている」。安定した職場の一つが病院やクリニックという地域は多く、住民の健康を支える医療機関は貴重な雇用も生み出してきた。ところが、経営に行き詰ってたたまないとならないところが出てきている。
医師の供給にも課題がある。福岡県こそ九州大や久留米大など4つの医学部があるが、それ以外は各県にある国立大が頼りで、医師の数は十分でない。このため、重要性が格段に増してきた在宅医療にまで手が回らない厳しい現実がある。CCHのような新たな挑戦をしようにも、中心になってくれる意欲あふれる医師がいないと難しい。
こうした地域事情を肌で知るメンバーは、病院・クリニックの経営改善や人材確保、介護施設や行政への助言などに走り回ってきた。病院再生では苦しくなった先を金融機関と連携して支援するケースも少なくない。医療報酬改定で年々医療機関の経営は難しくなっているが、資金の貸し手である銀行や信金としては地域社会が混乱するような病院閉鎖は何としても避けたい。そこでメディヴァに助力が求められることになる。
報告書は作っても、肝心の実行支援はしないという業者もいる。そうした苦い体験をした医療機関では、銀行に頼まれて顔を出しても「またコンサルか」と冷ややかにあしらわれることさえあった。しかし、実績が出るようになると先方の対応が変わってくるという。すでに3、4年一緒に再建に取り組んで目標を達成し、契約が完了した先も出てきたし、そうしたところからの口コミで新たな顧客がやってくることもある。入川さんは「これから重要なのは統廃合も考慮に入れて、地域の医療拠点を守ることです」と話してくれた。
九州に拠点を構えたことで、「地域でできること」の解像度が高まり、支援の幅も広がっている。メディヴァが実績を積んできた医療機関の支援、CCH、産業保健事業などを展開する支店は、一方で新たな知見や技術、情報をもたらす役割も果たしている。
その一例が福岡市と手を組んだ認知症フレンドリーセンターで、認知症デザインなどの蓄積を生かして成功に導いた。地元の放送局でキャスターとして活躍し、2010年に36歳で就任した高島宗一郎市長のリーダーシップのもと積極的な市政を進めるなかに、「福岡100」がある。人生100年を見据えて持続可能な街を目指す長期的なプロジェクトである。ここでメディヴァは認知症患者も住みやすい街づくりを支援してきた。
もう一つの政令指定都市である北九州市は、昨年市長に就任した武内和久氏のリーダーシップのもと、ITやロボットを活用しながら介護職員の業務の効率化や質を高める取り組みを進めている。「うむ、介護」という一風変わったタイトルの付いた北九州市の事業では、介護事業部の青木朋美マネージャーのもと調査分析からモデル策定、実証実験、評価など幅広く取り組んでいる。
労働環境の厳しさや不十分な処遇から介護職員の離職は全国で問題となっている。最先端の技術を駆使して解決を目指す北九州市の挑戦は、遠からず日本と同様の高齢化社会に直面するアジア諸国などへの普及も視野に入れた戦略的な取り組みで、メディヴァが目指す介護事業の世界観と一致している。
いま福岡支店の支援先は九州・沖縄にとどまらず、京都、鳥取、兵庫、愛媛など関西や中四国に広がり、入川さんはいつも十数件の案件を抱えている。一方、19年に開業支援をした茨城県土浦市のクリニックについては、今もオンライン中心に事務長のような仕事をしているという。
去年8月に加わった眞部芳幸さんは、北九州市の在宅介護を担当している。出身は大分県で、医療サービスが限られ何かあれば50キロ以上離れた大分市内まで救急車という地域だった。介護の仕事で弱者に手が行き届かない現実を見てきたことから、次の世代に残せるものをと考えて転職したという。
前の勤め先は「昭和の職場」で出勤簿も印鑑。さらに会議は集まっての対面が当たり前だった。20年間勤め、介護施設の管理者をしたが、IT化はまだまだというのを痛感していた。一方のメディヴァは令和の最先端で、オンラインで仕事がはかどるのは驚きだった。ただ、地域を支えるには人と接することが重要なのは変わらない。メディヴァには様々な人が集まっており、知識を共有できることは大きな魅力だという。
医療機関の労務管理や給与計算を支援するPPM部門の田村ひとみさんは、支店に詰めて執務することが多い。忙しそうに出入りする仲間を見て、ものすごく頭が切れる人たちが楽しそうに働いているという印象を持っている。福岡市出身で社労士の資格を持ち、医療機関での勤務が長かった体験から「メディヴァが入ることで経営がよい方向に向かうことは地域にも大きなプラスになる」と話す。
23年7月に加わった武内香月さんは週1、2回は出社するが、あとは在宅で子育てをしながら、地域の病院やこども園の支援などに忙しい。中央官庁でのキャリア官僚から佐賀県庁へ出向した役所勤めの経験を持ち、そこでは福祉や医療を担当していた。当時は新たな政策での成功事例ばかりに目を奪われがちだったが、今は経営が厳しい医療機関が抱える一つひとつの問題解決に地道に取り組んでいる。
視点の大転換を体験し、「どこにでもやる気のある人はいるが、やり方が分からないことが少なくない。そうした人材を巻き込み、助言することで経営の立て直しを図りたい」と話している。
大きく活動領域を広げている「西日本の砦」から生まれた福岡市認知症フレンドリーセンターには、アジアはもちろんのことフランスや米国からも見学者がやって来るまでになった。こちらについては、次回に紹介することにしよう。