RECRUIT BLOG
2024/12/02/月
寄稿:メディヴァの歴史
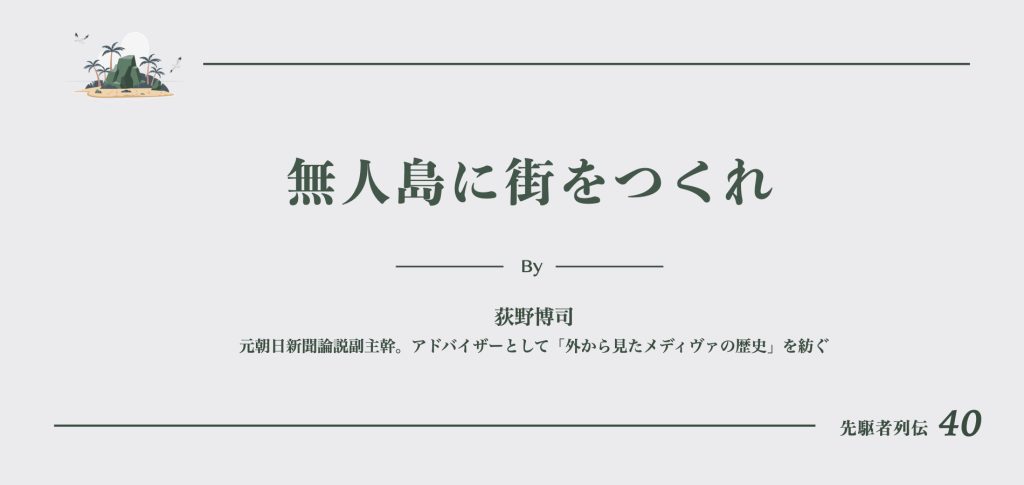
メディヴァには一般の会社なら当たり前の人事部が見当たらない。採用や研修、人事評価、異動などを取り仕切る中枢部門を敢えて置いていないのだ。人事評価も採用と同様にマネージャー以上の30人ほどが総がかりで取り組む。昇格については、その社員が次のレベルの役割を果たせるか否かを基準に判定して、最終段階の評価会議に推薦する仕組みだ。
評価会議では取締役とシニアマネージャーが社員ごとに評価し、その決定に応じて昇格、賞与、昇給が決まる。すでに自己評価、上司評価を経て上がってきたデータをもとにあらためて仕事の成果を評定するため、缶詰で3日半にも及ぶ作業になるという。すでに社員が300人に迫る業容となったが、このやり方は変えていない。
人材に関することは経営の根幹であり、役員や幹部社員全員で行うべしという信念からだ。評価、処遇はもちろん最重要事項だが、真の目的は人材を育成することと位置付けている。たしかに在籍している人をただ「出来ている、出来ていない」と評価しても目指すところに到達できる保証はない。全員が成長し、やりたいことを実現することがメディヴァの目指す「患者視点の医療変革」に直結するという考えだろう。
その人に足りないものは何か、さらには、どうすれば育つかについてまで論議するため、ときには一人の社員に1時間半をかけることもある。昇格が見えてきた社員には、フィードバックの際に次回までやるべきことが示される。「必ずやり遂げましょう」と大石さんは社員に呼び掛けている。
この評価会議でも岩崎さんが重要な役割を果たす。評価と昇格は全員で議論して決めるが、評価から賞与や昇給の数字を導き出す数式、ポジションごとの給与テーブルを検討し、必要に応じて改訂する役回りである。
ご本人に心構えを尋ねると、メディヴァを生態系にたとえて説明してくれた。「ビオトープってありますよね。その中で生物と栄養分、排泄物がバランスを崩さず循環して生物が生き続けるように、お金、仕事の成果、社会への価値、社員の精神的充足などがバランスよく循環しなければ企業も存続できません」
経営状態を見つつ、社員の実力と待遇のバランスに目を配り、メディヴァ内の循環を維持するということか。評価から賞与や昇給を出す数式とポジションごとの給与テーブルが「生態系」を保つ必須のアイテムだ。少な過ぎれば不満がつのり、多過ぎれば会社は赤字になる。それも単に均衡を保つだけでなく、より高いバランスを目指している。そこには会社の業績アップに従って全体としての待遇を継続的に高めているという自負がある。
さらに数式には表せないものの、充実感や社会貢献に対する誇り、自己成長感など、社員が仕事に求める金銭以外のものも同じ視野に入れ、全体が成り立つように配慮しているという。
さぞ難しい数式やテーブルが並んでいるのかと思ったが、「ごく単純なものです。ただ、どの要素に連動させるか、そこにどの数字が入るかが生命線で、頭だけで考えても失敗します」。実態を常に確認しながら調整するサイクルを回し続け、生態系を維持できていることに意味がある。
クラウドにバックアップされてはいるが、相当な機密資料なので簡単にはアクセスできない。社員の処遇を検討するなかで過去のデータが必要になった局面では、データを検索する岩崎さんの作業を全員が固唾をのんで見守るという。手作り感が詰まった会議室風景は以前から変わらない。
大石さんや小松さん、岩崎さんらの出身母体であるマッキンゼーにも人事部門はないと聞く。プロジェクトベースで動いているからで、最終的な評価はパートナーが担当して昇格に反映している。メディヴァの流儀には、世界有数のコンサル企業の影響もあるのだろう。
筆者がこれまでの取材で接した人々に共通するのは、話し好きで自らが目指す目標を熱心に語る姿勢だ。人材採用と評価、育成が意図した方向で機能している賜物ということだろう。前回に書いた「個性あふれる手作り感」もその一環であると納得がいった。
一般に人事部は採用や評価のほか社員の健康管理を任されることも多い。そこは永尾嘉康シニアマネージャーが率いる産業保健チームが担当している。本来は契約先の健康経営を支援する営業部門だが、本業のノウハウを生かして管理部門の一部も担う。人事部を置くよりも効率的で、経験を積むことで人材育成にもつながるという経営判断だ。何とも実務的なのもメディヴァらしい。
いま、注目されている人的資本経営については何を今さらというところだろう。長らく基幹メンバーが総がかりで採用や評価にあたってきたのだから、言われるまでもない。先ほどの産業保健分野に乗り出すときも、システム投資や企業買収でなく、まず永尾さんらを採用して一から始めている。無人島での街の作り手に最優先で投資してきたということだ。
一方で、組織が育ててくれると考え、軸足がしっかりしないまま会社を去るケースもある。自分のやりたいことを実現するためには、自律が求められるという厳しい側面もある。
さて、他に例を見ない採用や評価の体系は今後どうなっていくのだろうか。
今のところ定期異動がない。採用は部門のマネージャーが最終決定し、それは「親」と称する育成責任者になることを意味する。岩崎面接を突破したことでメディヴァ基準に達していると認められた人材を「人がほしい」と手を挙げた部門に委ね、じっくりと育て上げてもらう独自の制度だ。
この仕組みは10年ほど前から導入している。本人の志望の移り変わりや適性の見極めの中で、親となる上司も担当部門が変わることはある。キャリアチャレンジという仕組みがあり、年2回新たな分野への希望を申告でき、部署替えが実現する例もあると聞く。とはいえ人材の流動性が乏しくならないか。
新聞社に入ってから定年まで、引っ越しを伴う異動だけでも10回ほど、持ち場替えは数えられないほどだった筆者からすると、時間をかけて育てられる環境はうらやましい。一方で、マンネリに陥らないか、気にならないでもない。
メディヴァの原動力が「自分のやりたいことを実現する」ところにあるのであれば、従業員が500人、1000人と拡大しながらそれを維持することが可能なのか、新しい形が必要なのか。
岩崎さんは「組織的な特徴は自律。自分たちで考えて決めて結果を出す。社員の数だけ知恵があり、実行するパワーも増す」と語る。コロナの時には各部署がそれぞれ最善の方法を考えて組織的に実行し、業績も仕事の価値も落とさず乗り切れた。これが自律した組織である何よりの証明だという。この組織風土を維持できれば規模に関わらず、300人なら300馬力、1000人なら1000馬力になるという確信がある。
その問題意識を反映して生まれたのが「行動規範(コンピテンシー)」である。マネージャーたちによる全社横断の人財委員会のもとで、組織規模の拡大や事業の多様化、組織の階層化といった環境変化に対応する共通の物差しづくりに取り組んだ。
「Ownership」「Engagement」「Innovation & Value-Added」「Issue First」の四つの柱からなり、これまでの成長を支えてきた行動や考え方の特性を網羅している。創業から培われてきたメディヴァらしさを整理したものといえる。ただ、こうした規範は作るよりも浸透させる方が難しい。人財委員会が中心となり、マネージャーを対象にして具体的な事例とつなげて考える「言語化ワークショップ」も始めた。コンピテンシー以外にも様々な切り口でカルチャーの維持と発展に努めている。
自由闊達な気風を生かしながら組織をいかに拡大させていくのか。上意下達や形式主義を嫌い、人事部いらずで成長してきたメディヴァの行く手には、新たな挑戦が待っている。