RECRUIT BLOG
2024/10/11/金
寄稿:メディヴァの歴史
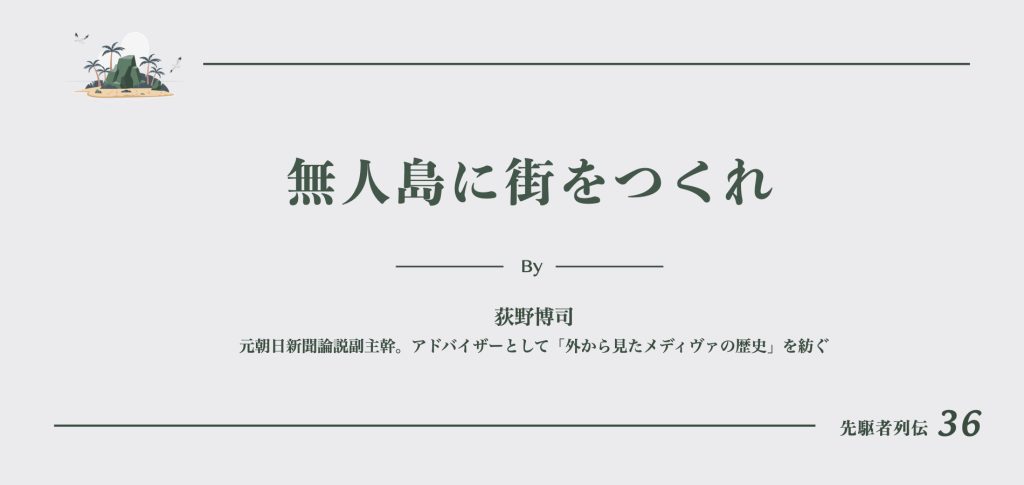
今では至るところで耳にするDX(デジタル・トランスフォーメーション)が国内で広く知られるきっかけは2018年9月の経産省レポートとされる。そこでは紙の情報を電子データに置き換えるような単なるデジタル化にとどまらず、組織体制や業務の進め方、さらには医療やエネルギー、交通など社会の重要なインフラまでデジタル基盤で変革していくことをDX化と位置づけている。
その経産省レポートから1年余。世界中がコロナ禍に翻弄される事態に突入し、否応もなくオンライン業務や在宅勤務が広がった。はからずもDX化が一歩進んだことになる。2000年の旗揚げ当時から電子カルテを積極的に導入し、その後もデジタル化を意欲的に進めてきたメディヴァ・プラタナスにとって、この数年間は自らの足元を見直して弱点を克服し、新たな態勢に転換する重要な時期となった。
林佑樹シニアマネージャーが中心となったDXチームが、イークでの業務プロセスの洗い出しと課題の整理を始めたのは2020年のことだった。イークは契約・予約・請求という重要な業務は早い段階からシステム上ですべて管理していた。とはいえ内容が複雑なうえ、アナログ運用で対応する部分が多いために作業の難易度は高く、職場の負荷は大きかった。
激変する環境のなかでDX化が急がれていたのはメディヴァ・プラタナスも例外でない。とはいえシステムや運用の見直しが業務の中断を引き起こさないように慎重に作業する必要がある。コストやリスクと最終的なメリットとを考え合わせた結果、プラタナスの稼ぎ頭で大きな効果が期待できるイークで思い切った業務改善に乗り出すことになった。
全体の業務フローを掌握して作業を進める仕事を託されたのは、20年11月にメディヴァに加わったばかりの中澤亜希グループリーダーである。前職の大手印刷会社ではシステム開発を担当していた。印刷業は今も重要な事業部門だが、いまや情報に関する総合産業に変身しDX事業開発が重要な柱に育っている。
以前から積極的にデジタル化に取り組んでいたイークで、中澤さんが期待されたのは、これまでの経験を生かしてDX化を加速させる役割だった。入社にあたって現場に近い職種を志望し、林さんが事務長を務める松原アーバンに加えイークを担当することになった中澤さんだが、いざ取り組んでみると驚くことばかりだった。
長年、開発現場に身を置いていた専門家としての第一印象は「想像を絶する環境」だった。サーバーが床に無造作に置かれ、使われることの少ない男子トイレ内に据えられているオフィスもあった。サーバーが故障した際の対策やバックアップなども不十分だった
まず床下を走っているLANケーブルや院内に設置されている多数のサーバー類を追いかける泥臭い作業に取り組んだ。各種システムの設計仕様書が見つからないためそれぞれが何を処理しているのかが分からず、一つひとつ端末機器と照らし合わせるしかなかったのだ。何者かわからないサーバーたちの「身元調査」である。
すでに連載の第7回から4回連続で紹介した通り、丸の内院から始まったイークの健診事業は、受診者の声を生かした丁寧な対応が高く評価され、急速に成長してきた。これまで業務が拡大するたびに新しい機器を入れ、膨らむニーズに対応してきた。
現場の事情を考えれば、やむを得ない面はあるし、それで大きなトラブルもなく良質の医療サービスを提供し続けてきたことは現場力の高さとして誇ってもいい。とはいえ、18年にメディヴァに入り、イークで事務長などを務めてきた深澤康祐マネージャーらもシステムの抜本的な改善が必要という問題意識は持っていた。しかし、ではだれが、どこから手を付けるのかといったノウハウは乏しかった。
契約先である大企業や健保の基準や視点でセキュリティを構築しないといけない。それが林さんや中澤さんらDXチームの見立てだった。個人情報保護法が強化されたほか、コロナ禍のなかで医療機関へのサイバー攻撃が増えた時期でもある。
最初に手を付けたのは、リスク調査と対応策の提案だった。つまり、「サーバーが止まったら業務にどのような影響が出て、復旧までにどのくらいかかるか」と「どんな対策をとるのか」ということだ。費用もにらんで、対応策については「松竹梅」にランク分けしてプランを出したそうだ。
イークメンバーとの検討作業を経て、「停止後半日での復旧」を目指してシステムと事務態勢を整えることになった。具体的には、不足していたバックアップの確立、サーバー稼働の監視やトラブル時の対応策の整備だ。重要な業務を処理しているサーバーの機能を外部のデータセンターに移設する作業は、健診システムの全面更新のタイミングに合わせて実行した。
もう一つ力を入れたのが、サイバーセキュリティーである。外部から攻撃されるリスクは確率的には低くても、被害に遭うと取り返しがつかない。単純なコスト計算で済む話ではない。イークを率いる白根真ゼネラルマネージャーが、交通事故のリスクにたとえて「いつ遭遇するか分からないからこそ、直ちに備えをしよう」と決断したことは心強かった。
防御の壁をつくるには、存在する穴を突き止めなければならず、ネットワークの可視化が欠かせない。中澤さんがケーブルを一本ごとに追いかけたのは、弱点を洗い出す作業でもあった。全体図を描けて、ようやくシステム全体の弱点が浮かび上がるからだ。
これまでは個々のイークの事務長がシステム回りもみていたが、中澤さんが一括して対応したことで気がかりな点も出てきた。日々の実務に取り組むスタッフとの意思疎通が不十分になったり、自らの問題ととらえる当事者意識が薄らいだりする懸念である。そこでグループリーダーの田中祥代さんがDXとイーク運営の二役を果たして、橋渡しをすることになった。
日々の業務に追われる事務長に負荷がかかり過ぎないように配慮しながら、「DX化と業務をどう進めるのか」を考えるのが田中さんの仕事だった。当人は今年4月から、深澤さんの後任として表参道院の事務長を務めている。
仕事の山場は、健診のための基幹システムの切り替えだった。それまでのものは丸の内院のために導入されたもので、25年2月のオープンが予定されている渋谷院が加わると耐えきれず、データ処理が遅延する事態が予想された。そこで24年4月、多店舗展開に対応できるシステムに置き換えた。
イークのメンバーが検討してきた「コネクトセンター」の開設についても、システム面から支援した。各院に散らばっていた契約や予約などを一体で対応するもので、有楽町近くのビルに置かれ、この9月から稼働している。単に電話を受けるだけでなく、利用者情報をレベル分けし、難易度に応じて対応者を振り分けるようにしている。さらに生成AIを入れ、電話のやり取りをTEXT化したうえで要約をレポートとして残せるようにした。
他社の事例も知る中澤さんによれば、「これほどうまくいったプロジェクトは初めて」。とくに基幹システムの切り替えは、組織の全員が一丸となって取り組んだおかげで、キックオフからリリースまで1年ほどで完了している。2年程度かかってもおかしくない作業だけに驚異のスピードといえる。トラブルが起きた時に総出でデータの再入力作業をした姿は、みんながDX化に取り組むようになった象徴と映ったそうだ。
すでに新しい健診システムなどは、現場の事務長が管理して運用している。DXチームとしては、新年度に婦人科オンラインを改良することを考えている。情報連携がしやすくなり、問診の結果を踏まえた受診や治療などの把握にも対応する。
イーク側で作業に取り組んだ深澤マネージャーは、「あくまでもITコンサルを入れたという姿勢で臨み、ベンダーの選定や最終評価はこちらで行った」と振り返る。仲間うちの馴れ合いにならないように気を付けたことで、DXチームも外部でも通用するノウハウを積み上げることができ、Win-Winの結果につながったと見ている。
いまDX化はメディヴァ・プラタナスの多くの医療機関に広がっている。CCHメンバーの病院に対するネットワーク環境やパソコンなど端末の整備、セキュリティ対策といった土台部分をDXチームが整えた。同善病院は計画して1年でネットワークの整備から電子カルテまで完了した。また、水海道さくら病院は24年11月から電子カルテの導入作業に入る。「このスピード感にはイークやプラタナスでの対応が生きている」と林さんは話している。
これから取り組むのはグループ外の中小病院などへの展開だ。厚労省の統計によれば、電子カルテの普及率は400床以上の大規模病院では2020年の段階でも91.2%に達しているのに、200床未満の小規模病院は48.8%と5割を割っている。今でも紙カルテが当たり前の世界が広がっているわけだ。
システム化を始めている中小病院でも、ともすれば増築を重ねて「ぐちゃぐちゃ」になりがちなうえ、専門家がいないと小手先の対応になる。「情報システム代行サービス」として、DXチームの派遣やシステム回りの問い合わせ窓口の代行、システム担当者の採用支援などを手掛けようとしている。
医療機関の業務をシステム化するといっても、一足飛びにAIの導入などできるはずはない。まずアプリケーションを活用して業務をデジタル化するという土台作りが欠かせず、DXチームの活躍の場がある。それで初めて思い切った業務効率化の道が開けることになる。
医療の分野ではIT技術を生かしたスタートアップ企業がさまざまな取り組みを始めている。こうした会社にとって、多くの医師や看護師らを擁し、四半世紀にわたって蓄えた知見があるメディヴァ・プラタナスとの連携は心強い。そうした企業が温めている事業計画に、医師がオンコールで指示した内容を文章化して、さらに書式に合わせたサマリーをつくるというものがある。ここではメディヴァとIT企業が手を組み、東京都が医療機関を対象に実施するAI技術活用促進事業に手を上げることにしている。
また、日常の生体情報をもとに、糖尿病患者一人ひとりに食事や運動を提案する医療支援サービスに取り組んでいるスタートアップ企業に対して、24年9月に出資している。医療の将来をにらんでの投資である。
最後に苦い体験を取り上げる。3年ほど前にメディヴァもホームページを乗っ取られたことがある。いったんサイトを閉鎖したが、ウイルスの完全な除去は難しく最終的に捨てる決断をした。2か月で仮復旧にこぎつけ、その後半年をかけて復旧させたが、HP上のそれまでのデータが消えたのは痛恨事だった。
仮復旧までの間には、コンタクトを取ろうとしたが、いくら探しても見つからないといった苦情が寄せられた。ネット空間に存在を示せないことがもたらす深刻な影響やサイバー犯罪の怖さを思い知らされた。
近年、大阪や徳島、岡山などの病院がサイバー攻撃の被害に遭い、機能が麻痺したり、患者情報の流出が懸念されたりする事態に陥っている。医療が止まれば患者の生命を危険にさらしかねないし、情報の流出は医療機関と患者の双方に致命的な打撃となる。
「最悪の事態を招かないためには、サイバーセキュリティーの強化につながるDX化は喫緊の課題となった」。林さんらDXチームの面々が抱いている確信である。