RECRUIT BLOG
2024/07/16/火
寄稿:メディヴァの歴史
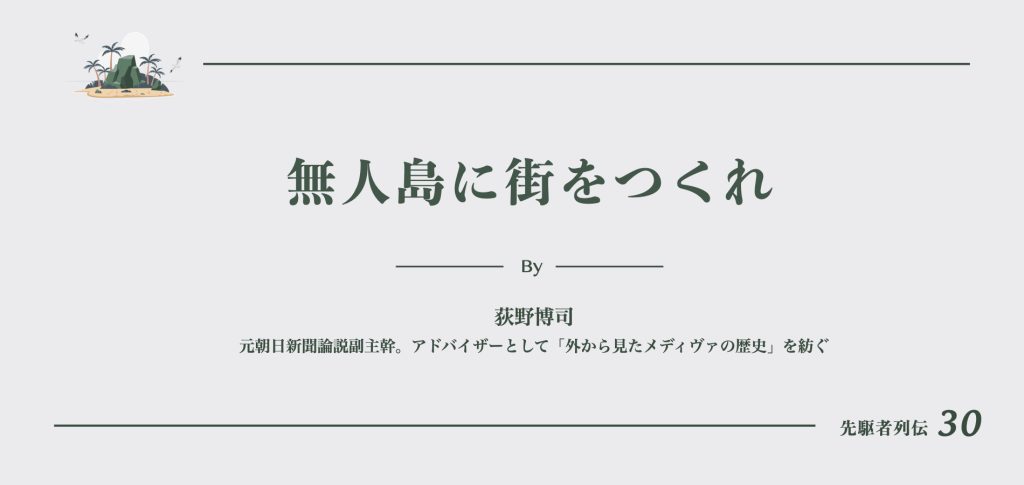
先進的な在宅医療の拠点として、全国的に知られる桜新町アーバンが生まれたのは2005年5月。経営に行き詰った医院が銀行の仲介によりプラタナスの一員として再出発したことに始まる。しばらくは以前からの透析クリニックを中心に運営されていたが、09年に遠矢純一郎医師が院長に就いたのを機に、外来機能を備えた「在宅療養支援診療所」に転じた。
いま、桜新町アーバンに属している人員は100人ほど。訪問診療、訪問看護とナースケア・プランニング(ケアマネ)を担当する在宅医療部、外来部のほか、ナースケア・リビング世田谷中町(略称:かんたき)、認知症在宅生活サポートセンター(同:にんさぽ)も抱える。これだけの大所帯は、在宅医療に打ち込んできた遠矢院長や五味一英在宅医療部長と田中啓広外来部長の連携、医療スタッフの熱意や工夫、村上典由シニアマネージャーらメディヴァ勢の実務力が支えている。
取り組みで特徴的なのは、患者自身や家族と向き合って治療方針を決める姿勢の徹底だ。このためには診察や看護、介護に携わる専門職のチームプレーが欠かせない。また、終末期の患者では自身の死の時期を意識する中での不安も出てくることから、本人がどのような思いを抱えているのかを意識して丁寧に向き合い、できるだけ本人の思いを叶えることを心がけてきた。
その一端ともいえる新プロジェクトが進行中だ。
これまで、人々の人生終盤の暮らしに伴走してきた看護師らによって生まれた全44ページの冊子『人のさいご』である。3つのパートに分かれ、1章「人のさいご」では、自宅で最期を迎えたいと考えたときに訪問診療や訪問看護をはじめとするケアの専門家が支えてくれることや、病気ごとに身体機能の低下の過程が異なることなど、専門的な事柄を説明している。
本編といえる2章「いのちを閉じていく自然な経過」では、これまで当たり前にできていたことが難しくなり「病状が押し寄せてくる」という印象を持つかもしれないこと、飲食や排泄が減っていき、眠っている時間が長くなることなどを取り上げる。
3章「いのちを閉じるとき」は、手足の色や息づかいが変わっていく過程が描かれ、「お別れの時は、ふとした時に訪れます」として、たとえ死に目に遭えなくとも「それまで一緒に過ごした時間が大切なのです」と周囲にいる大切な人たちにも語り掛けている。
つくったのは、桜新町アーバンの看護師國居早苗さん、林瞳さん、尾山直子さんの3人と、メディヴァの神野真実さんだ。優しいイラストも添えられ、平易な言い回しながら人生の最期に向き合う医療専門職の目が随所に感じられる内容に仕上がった。
訪問看護の管理者でもある國居さんは25年間現場に立っているが、人が亡くなるときについて書かれたものは家族向けのパンフレットが多く、命を閉じていく本人も安心して読めるものが必要ではないかと感じていた。独自のものを作れないか、と林さんと3、4年前から話しており、コロナ禍を経て、尾山さん、神野さんも加わっての作業が始まった。23年3月のことだった。
看取りの現場に立ち会ってきた看護師たちは、目の前の患者さん一人一人の状況や、考え方にあわせて伝えてきた。その蓄積を1冊の本に留めるために言葉の選び方には慎重になった。繰り返し原稿を直しては寝かせ、また書き加える。制作の過程では患者さんご本人のお話もうかがった。そこでは「伝える相手は誰か。誰に向けているのか」という鋭い指摘があった。当初は家族と本人の双方に向けて書いていたが、確かに視点があいまいになる。そこで本人向けとふりきり、家族へのアドバイスは別に添えることにした。それにより作業が一気に進んだそうだ。
メディヴァの神野さんは、家で亡くなるとはどういうことなのか、閉じた世界を外に伝えていきたいと考えて参加を決めた。一般に死をイメージする時、亡くなるその瞬間を想定することが多いが看護師たちの話を聞くうちに、死ぬことは点ではなく、経過の線として捉えられるようになったという。イラストやデザインは専門家とともに練り上げ、デザイナーはお家でさいごを過ごすご本人のもとにも足を運び、イメージを固めてくれた。
尾山さんが24年5月の東京新聞(中日新聞)のコラムに、この本を紹介したこともあり、問い合わせや注文が次々と舞い込んだ。ようやく7月から仕事の合間を縫っての発送作業に入っているが、これまでの注文は2000冊に達している。出版不況が続くなか、書店などの流通ルートに頼らない自費出版としては異例の反響と言える。
在宅医療部の活動の成果としては、3冊目の書籍となる。このうち19年の『在宅医療経営・実践テキスト』(日経BP)は22年12月に改訂版が出され、21年9月には入門書『ポケット介護 みんなで支える在宅医療』(技術評論社)も上梓した。そこに『人のさいご』が加わったことになる。
このほかにもスタッフの発案で始まったイベントは少なくない。65歳以上で自立している高齢者を対象に月2回開いている「アーバンちいき食堂」、遺族の皆さんの語らいの場となる「こかげカフェ」などの催しが続いている。
高齢者では老化によって身体機能の低下は避けられず、「治癒」を目指すことは難しくなる。その先には看取りが待つ厳然とした事実もある。桜新町アーバンが取り組んでいるのは、患者と家族の暮らしの質(QOL)を高めることだ。言い換えると、向き合う人たちの個別性や多様性を受け止めながら、満足度を最大化するにはどうすべきなのか、を考え続けることだろう。
こうした輪の中で外来部の役割も大きい。現在の診療科目は内科と心療内科で、用賀アーバンと同じく家庭医としてのプライマリーケアが中心だが、桜新町アーバンには要介護状態の患者も多く、老年科という性格を帯びている。心療内科でも認知症などの高齢者が多い。村上典由シニアマネージャーとともに事務長を務める高田哲也マネージャーは「外来と在宅の狭間の人が多い。以前、田中先生と一緒に調べたら平均年齢は70歳だった」と語る。
外来部長の田中医師は、北海道室蘭にある北海道家庭医療学センターで学んだ。これからの医療ではプライマリーケアがきわめて重要であると考えたからで、2016年、家庭医の重要性を内外に発信し、実践しているプラタナスへの参加を決めた。現在は週のうち3日半を外来に、1日半は訪問診療に充てている。
内科の一般クリニックでは極めて珍しいのが送迎サービスの充実だ。駒沢大学駅から用賀駅の間で環八や世田谷通り、駒沢通りに囲まれた地域の患者は、送り迎えの車を無料で利用できる。このために専任の運転手を用意してきた。在宅医療という後備えを準備したうえで、ぎりぎりまで外来で診るためだ。おのずと地域内にあるシニア向け住宅、介護住宅とのつながりも密接になっている。
送迎サービスの利用者は1日10人前後。101歳のお婆さんが通ってきている例もある。田中医師は「他のクリニックでは家族が薬を取りに来るだけという事例もある。しかし、患者を診なければ、薬効も分からない。患者には来院してもらえる環境を整えてきた」と話す。外来から在宅医療まで継ぎ目なく診られる態勢を整え、自分で動くことが難しくなっても家で暮らし続けられるように支援するのが目標だ。
患者サービスを手厚くすることはコスト高につながる。高田事務長は「外来の収益性は低いが在宅もある。点数では測りきれないものがある」としながらも、世田谷という医療の激戦地で収益力をどう高めるかという難題に取り組んでいる。
いま外来部門と在宅医療部門のオフィスは、直線距離でも2キロ弱と離れている。在宅医療部の急拡大で外来が入っているビルにはとても収まらないし、その近隣に手頃な物件がないためだ。その分スタッフ間の交流に心がけるほか、外来で人手が不足したらカバーする態勢を整えている。助け合いは心強いが、一か所に集まり日ごろの自由な論議の輪がさらに広がったならば、「さいごまでお家で」を掲げる桜新町アーバンにさらなる化学反応が起きるような気がする。