RECRUIT BLOG
2024/06/28/金
寄稿:メディヴァの歴史
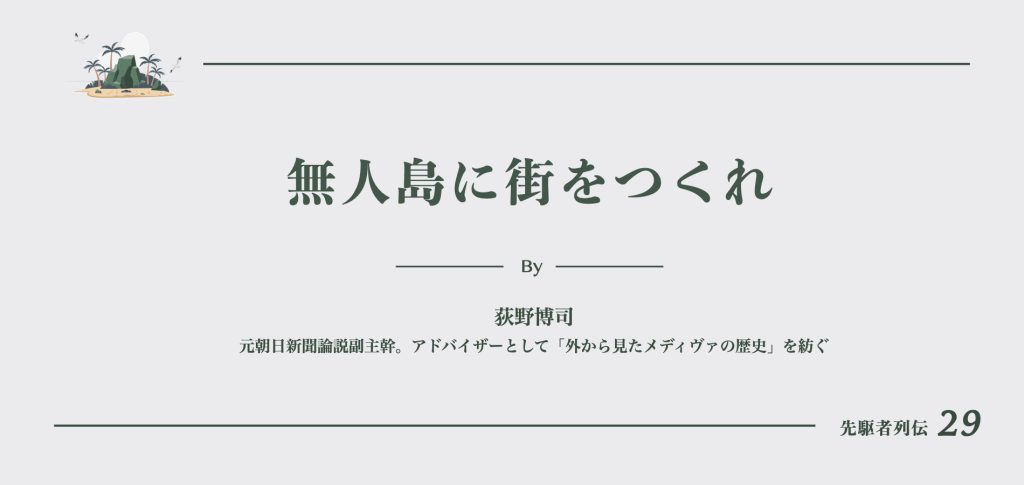
患者視点の医療経営、地域包括ケアの基盤づくり、産業保健の推進、病院再生・・・。ときには海外にまで活動の場を広げてきたメディヴァだが、その原点にあるのは東京・世田谷を中心に展開してきたアーバンクリニックだろう。連携する医療法人社団プラタナスが医療の根幹を担い、その経営・運営の支援をメディヴァが支える二人三脚での25年が、荒れ果てていた無人島にいくつもの街を築いてきた。
近年、誰もが予想もしなかったコロナの大激流に翻弄された。一方、健康保険財政が窮迫するなかで厚労省による診療報酬の改定も続く。各アーバンクリニックは、それぞれが今後の進路をしっかりと見定める時期を迎えている。これから数回にわたり、その最前線を訪れることにしよう。
最初に訪ねたのは用賀アーバンである。世紀替わりまで4週間を残すだけの2000年12月4日に開院した。メディヴァが設立されて半年後のことである。医療に興味のあるビジネスマンとビジネスに興味のある医者によるブレインストーミングから始まった挑戦が大きな一歩をしるした。患者視点での医療変革を目指すメディヴァ・プラタナスの人々にとっては、頼もしい「旗艦」として今日まで地域医療を支えてきた。
周囲の期待を一身に集めてスタートし、着実に実績を積み上げた時期については、すでに連載の折々に紹介している。その後、隣のビルに移転して、当初の1フロアから2フロアに拡大した。2階にも二つの診察室のほか、内視鏡、X線、エコーなどの検査室がある。常勤は野間口聡プラタナス理事長、田中勝巳院長、佐藤俊一医師の3人。さらに非常勤医師が4人、ナース8人、薬剤師5人、事務8人の陣容だ。
「来院患者は多い。一人の先生に頼る多くの診療所と違って、得意分野を持つ複数の医師がいるので評価されるのだろう」。開院から診察にあたってきた野間口理事長は語る。世田谷の特性は人の流入が多いことだ。こんなに長くやっているのに、初診者は少なくない。医療機関にかかろうとする人の多くはまずネットで探すため、定評のある用賀アーバンがヒットするようだ。
開院にあわせて踏み切ったカルテ開示は25年間やっているが、大きなトラブルはない。患者に読んでもらっても支障はないし、分かりやすく書くように努めている。カルテに詳しく書いている医療機関は他にもあろうが、それを患者に見せるには覚悟がいるだろう。サマリーや投薬状況も書かれているので、別な医療機関で受けたときにもこれを持参すれば病気の詳細や治療経過が分かる効用がある。
街のお医者さんの判断基準は、患者様が適切な医療を受けるための「ゲートキーパー」となり得るかどうか。診られる範囲が広いことは肝要だが、最も重要なのは適切なタイミングで2次・3次の医療機関に紹介する判断をすること。用賀アーバンが心して取り組んでいることである。メディヴァとプラタナスの連携により、医師は目先の収支に過度に神経をとがらせることなく、求められる医療に打ち込める環境にある。
とはいえ、順風満帆で四半世紀を駆け抜けてこられたわけではない。
患者本位を掲げる用賀アーバンにはコスト高の体質がつきまとう。医師や医療スタッフが多く、必ずしも効率が良くない。院内薬局はその一例だ。薬の在庫を抱え、薬剤師の確保も欠かせない。ただ、院内薬局ではカルテを共有できるので、処方の漏れなどがあれば直ぐに指摘してもらえる。来院者にとっては診察と薬の受け取りが一度で済むうえ、疑問があれば主治医に直接聞くこともできて好都合だが、その分クリニック側はコストが膨らむ。
2003年から在籍する田中院長によれば、以前から大きな利益が出ることはなく、小さな黒字を積み上げてきた。しかし、2018年度は赤字に転落した。薬の仕入れに伴う費用増という一時的な要因もあったが、地域の医療機関の競合が激しくなり、新患の伸びが鈍っているのは確かだった。当時の事務長だった越路公雄マネージャーは度々田中院長と対応策を話し合ったと振り返る。
治験に取り組んだり、医師側のパフォーマンスのモニタリングをしたりした。待ち順番の表示システムも入れ、患者サービスの充実も心がけた。また、2階を活用し、週末にはインフルエンザワクチンの集中接種に力を入れた。「診療サービス向上委員会」を設けて、職場環境の向上にも取り組んだという。こうした取り組みの多くは今も続いている。
一段と厳しい試練が訪れたのはコロナ感染が広がりだした20年初頭からである。この年度は再び赤字に転落する。
コロナでは手探りでの対応を迫られた。当時多くの医療機関はかかりつけ患者であっても感染の疑いがあると診療を拒否し、「発熱患者は診ません」という張り紙をするところも多かった。しかし、用賀アーバンは、かかりつけ医として診られる限りの患者に向き合う姿勢を貫いた。そうでなければ長い年月をかけて築いた地域との信頼関係は守れなかっただろう。
通常の診療としっかりと分けるため、院内感染を防ぐ手立てを講じた発熱外来の時間を設けた。当初は診察を昼時間(正午からの30分間)に充てたため、一般外来との転換に伴う消毒などに多くの時間が割かれた。その後、朝の時間帯に移したものの、ここでもタイムロスは生じて経営には打撃となった。
風邪などの症状が出た段階の急性期患者も生活習慣病での定期受診者も、誰もがいつでも気軽に相談して掛かれる。それが用賀アーバンの誇るビジネスモデルだった。ところが発熱外来の時間帯を設けたことで対応できる時間が減ってしまった。ビル内に新たな専用フロアを確保して、発熱外来を常時オープンするアイデアもあったが、院内感染を防ぐ医師や患者の動線の確保、医療施設としての申請の手間などを考えると、実現は難しかった。
かかりつけ医としての責任を果たしながら経営を維持するために、戦略的に「やること」と「やらないこと」を選別して効率化を図った。スタート時から掲げてきた小児科の看板を下したのはこの時期だ。それまで乳幼児の患者は着実に増えてきた。それがコロナ対策で子どもが外に出なくなったことで風邪やインフルエンザなどの感染症が一気に減り、小児の患者が姿を消した。今後、世田谷区でも子供人口が減ることが予測されるうえ、周囲に小児科の専門医院が増えている。これを機に小児科の専門医はおかず、内科医が子供を診ることにした。
開院の時から目標にしている子供からお年寄りまでのホームドクターであることに変わりはなく、今でも親子連れの患者は少なくない。しかし、苦渋の決断だったのは確かだ。「率直に経営が危ないと思ったときもあった」と田中院長は当時を振り返る。どうにか苦境をしのげたのはコロナワクチンの接種だった。休日返上で取り組み、会社などの職域にも出かけていった。メディヴァからも応援部隊が参加し、休日の事務方を担った。
23年5月、コロナが5類に変わったことで、田中院長や事務長を引き継いでいた浅野悠グループリーダーは大きな選択をする。発熱外来を撤廃し、発熱している患者の受診人数や時間の制約を解除したのだ。田中院長は「弱毒化したこともあり、緩やかな空間の分離で対応することにした」という。マスクができない患者や咳のひどい患者は個室で待ってもらうが、緩やかな症状の人は普通の待合室に。コロナは今も侮れないが、院内ではマスクを外さず、しゃべらないことを厳格に守ってもらうとともに、待合室の椅子を同じ方向に向け直して患者が向き合う機会を減らすことで対応している。
この効果はすでに表れている。浅野事務長によれば、内科系では年齢層は高めになる傾向があったが、現在は40~50代の働き盛りが増えている。熱があってもすぐに診てもらえることから利用者が増えたようだ。一方で一般の患者が大きく減ることはなかった。どうにかピンチを乗り越えたといえる。
次の打撃は今年4月以降の診療報酬だった。点数は軒並み下げられている。例えば、コロナ期に設けられた重症度チェックのトリアージ料は23年5月まで300点だったのが147点に下げられ、24年4月からはゼロになった。コロナと判明した後の診療加算も23年5月までは250点付いたが、その後はなくなっている。コロナ特例は次々と打ち切られてもコロナ患者の来院は続き、一般患者に比べて対応に手間がかかるのは変わらない。点数だけが下がり利益率が悪化した経営を、患者数全体の回復が下支えしている。
安心してはいられない。6月から慢性、生活習慣病の分野でも診療報酬にメスが入れられた。生活習慣病の患者に漫然と薬を出すのではなく、きちんと指導をして生活習慣の改善を目指さないといけないことが診療報酬の仕組みに反映された。療養計画書を作り、生活習慣の改善方法について患者と合意した時のみ従来のレベルの点数がつく。これができなければ、一患者当たりの点数は約3分の1に削られる。保険財政が厳しいなかで厚労省は手を変え、品を変えて、医療現場に変革を迫ってきた。
元々希望する患者に対してはメディヴァの保健事業部から派遣された管理栄養士が生活改善指導にあたっていた。薬に頼らず生活習慣病を治すことは用賀アーバンの精神にも合致している。適切な時期に適切な検査をし、丁寧な指導に努めて患者の健康を守るかかりつけ医としての実力を示す好機ともいえる。
課題は対応すべき患者数が多すぎることだ。用賀アーバンでは月に1500件程度が生活習慣病での来院だ。まずは療養計画書を100%作成し、医師それぞれがやっていた作業のスケジューリングを一つにまとめた「外来パス」を作り、効率的に指導する環境を整えることにした。また、検査や栄養指導なども計画書に盛り込み一体で管理するようオペレーションを組み替える方針だ。
ほかにもスマートデバイスを使った健康増進や理学療法士も加わったオンラインでの助言などのアイデアがある。すべてが保険では賄われないし、患者によっては保険以上の取組みを求める人もいる。さまざまな要望に対応するために、プラタナスとしての自費メニューも考える必要がある。浅野事務長は「用賀を健康な人が多い地域にできればいい。脱落させない健康指導が大切だ」と話している。
基本的には来る者は拒まずの自然流でやってこられたが、生活習慣病対策に本腰を入れるなら、これからは用賀アーバン独自のサービス、つまりホームドクターが担当する健診というメリットを生かす必要がある。プラタナスの仲間であるイークが開拓するのが大手健保なら、こちらは区民健診や中小企業のニーズを掘り起すことになる。
医療と経営のプロが組んでこれほどハッピーに回っているのは稀有な例、と野間口理事長は胸を張り、「クリニックが僕らの力を吸収して大きくなってきたイメージだ」と付け加えた。田中院長は「用賀はプラタナスの『聖地』。着実に黒字を出し続け、10年先でも20年でも持続していくのが理想だ」と語っている。
すっかり街になじんだプラタナスの「旗艦」は、あらたな航路を拓きながら海原を進んでいる。