RECRUIT BLOG
2024/06/10/月
寄稿:メディヴァの歴史
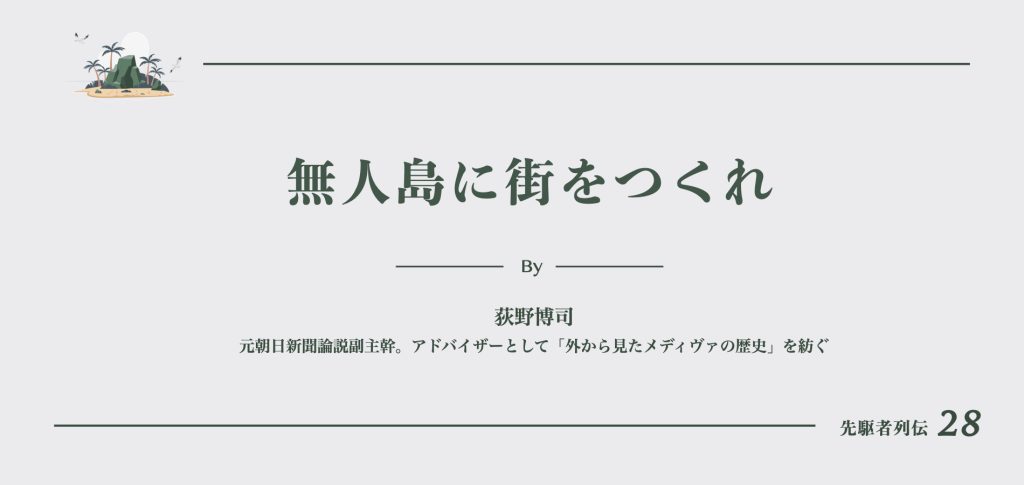
政府が進める地域包括ケアシステムの説明によく登場するイラスト図、役所言葉でいうポンチ絵がある。「厚労省」と「地域包括ケア」で検索すれば簡単に見つかるはずだ。図の中心に位置するのは住民と家族で、それを取り囲むように医療、介護、生活支援・介護予防が置かれ、さらに相談窓口として地域包括支援センターやケアマネジャーも配置されている。
地域のケアといえば、どうしても医療と介護に焦点が当たりがちである。しかし、コンサルティング事業部のマネージャーも務める臨床医の久富護さんは、これからの重要なテーマはインフラ、つまり住まいなど高齢者の暮らしを支える領域だと強調する。体調次第では医療機関に通院や入院することもあるし、さまざまな介護サービスや生活の支援も受けるが、基本にあるのは自宅や高齢者向け住宅での暮らしであり、その環境整備を疎かにしては「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで」という理念も掛け声倒れになりかねないからだ。
ここでもメディヴァに求められている役割は大きい。いまコンサルティング事業部が中心となって取り組んでいるのがLTH(Life Time Homes)の事業化、つまり高齢になってからも安心して住み続けられるサービスの開発である。
このプロジェクトには長い助走期間があった。
日ごろから医療と介護の現場を知るメディヴァの人々の多くが、「人生100年」を最期まで、できるだけ健康に、自分らしく、自宅で過ごしたいニーズが高いことは肌で感じてきたはずだ。多様な事業を展開している総合力が生かせるはずだ。ただ、息長く続けられる事業に育てるには、患者や家族のニーズ、そして経済的な条件などをしっかりと見極めなければ行き詰まる。
実は政府も同じような模索を続けていた。2019年度に国土交通省が実施した「高齢者向け住宅の実態把握事業」や21、22年度に経産省が手掛けた「ヘルスケアサービス社会実装事業」の背景にもそうした問題意識があった。メディヴァはこうしたプロジェクトを積極的に取りに行き、住まいや暮らしの実態を調べることで患者や家族のニーズを探った。
国交省の高齢住宅の調査事業を手掛けるなかで、いくつもの学びがあった。たとえば、高齢者の多くは住まいについての確たる将来計画は持っておらず、体力が落ちて生活に不安が生じた時や自立した生活が送れなくなってから考える傾向が強かった。子供世代との同居による住居の建て替えやリフォームが期待できない世帯が増えていることもデータで裏付けられた。
こうした成果を踏まえて、コロナ禍の20年ごろには、社内には高齢者の在宅生活に関心のある社員が意見を交換する自主サークルも誕生している。
さらに経産省の「ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金」に手を挙げ、実証実験に取り組んだ。高齢期を3期に分け、心身とも元気な1期にしっかりと予防し、不調が出てきて老いを感じる2期には対策を講じ、かなり老いてきた3期も適切な対応で自分らしく安全、安心に過ごすという考えを基本に据えた。
21年度は1期と2期の計16人を対象に支援サービスを試みた。柱となる「棚卸健診」では体力や姿勢、食事、睡眠、認知力、意欲など幅広い分野について一度しっかりとチェックし、その結果をもとに医療職が3か月間、心身の健康を保つための睡眠や運動などのアドバイスをした。一方、住まいを写真に撮り、転倒事故につながりかねないコード類の整頓など身近に潜むリスクを見つけては、改善してもらったりもした。
ただ、これだけでビジネスになるかというと厳しい。それでなくても健康に自信のある人ならば、わざわざ有料の検診を受ける気にはならないし、それなりの収入が見込めなければ多くの医療機関が導入することは望めないからだ。
そこで翌年度は住宅に焦点を当てた実証実験を手掛けた。東京・台東区の同善病院と共同で家族向けのイベントを開催し、認知症患者の視界が体験できるARグラスや運動機能が制約される高齢者スーツを実際に装着してもらい、高齢になった家族にどう安全に暮らしてもらうかを一緒に考えてもらう機会を設けた。
こうした取り組みを重ねることで行きついた一つが、センサーを活用して在宅の生活実態をリアルタイムで把握できる仕組みである。ベッドセンサーや人感センサー、ドアの開閉センサーを組み合わせ、緩やかに見守ろうというのだ。離れて住んでいる家族に向けたサービスという性格をあわせ持ち、高齢者を抱える子供らが感じる日常的な気がかりを軽減する結果にもつながる。何となく家族と高齢者がつながっているという安心感がもたらされる。
さらにデータは医療にも活用できる。家族のスマホ端末に示されるのが高齢者の暮らしぶりや活動状況、言い換えれば安否であるとすれば、医療専門職に向けてはより詳細なデータが送られる。日々の身体状況をプロの視点で確認することで、必要な指導や治療につなげることも期待できる。すでに電気ポットの使用状況で高齢者の安否を伝えるといったサービスは実用化されているが、これでは安否確認の役には立っても健康状態は分からない。医療の目が関わることで、質の高い見守りができるだろう。
例えば、年を取ると眠りが浅くなり、夜間のトイレ通いは増えがちだ。そこでセンサーが睡眠と覚醒のリズムやトイレの頻度などをつかめれば、より良い睡眠への工夫を助言し、すでに飲んでいる薬の処方を変えることもできる。このようにITを活用して高齢者の在宅生活の質を高め、家族も安心できることで、施設に入らず家で過ごせる期間を伸ばせる。
LTHの開発メンバーの一人、鮑柯含さんによれば、海外では自宅でも早い段階からセンサーを使って遠隔見守りを導入していることを、視察から戻った大石さんから聞き、有志サークルでの雑談のなかで形が固まってきた。
LTHの一環として、連載の第12回で紹介した認知症デザインの活用も期待できるだろう。自宅での療養では排泄の問題は深刻だ。認知度が落ちたことなどからトイレ外で粗相をするようになると、後始末をする家族の精神的なストレスは極めて大きくなり、患者も自信を失う。その結果、施設や病院に逆戻りという事態を防ぐためには、トイレの位置が分かるように扉の色を塗りかえたり、そこまでの経路を分かりやすく示したりする工夫が有効となる。
認知症デザインを英国から採り入れた海外事業部の木内大介グループリーダーは「地域包括ケアの対象者は認知機能が低下した軽度の人から、重い病気を抱えた人まで幅広い」という。重度の人には適切なサポート態勢を整え、自立している人は現状を維持したうえで、できる範囲を広げる支援が欠かせないが、そこに認知症デザインの出番がある。
また、リンナイや西部ガス、福岡市と協力して、認知症の人たちに開発プロセスに関わってもらい、誰もが安心してずっと使えるガスコンロを開発した。この2月には一般向けの販売が始まった。また、メディヴァが運営する福岡市認知症フレンドリーセンターにも展示されている。
高齢者でも聞き取りやすい音声案内、表示の見えやすさや間違えにくさを追求した大きな文字表示、配色に工夫したスイッチ回りなど、メディヴァが蓄積した知見が随所に生かされた。認知症になっても初期に環境を整えれば、自宅で長く住み続けられ、家族のために得意な料理を調理する楽しみも続けられる。これも人生100年時代の住まいづくりに欠かせない視点だろう。
「LTHは実証段階で、無人島にできた新しい街といえる段階ではない。開墾中というところ」。鮑さんは控えめな口ぶりで語り、開発チームの青木朋美さんや電動車いすに取り組んだ目黒ひかりさんもうなずく。たしかに日常生活のきめ細かな支援や自宅療養の環境の整備、亡くなった後の財産の整理や信託など、高齢者の生活の周辺には手を付けるべき領域が多く残っている。とはいえ、メディヴァの各所に蓄えられた知識や人脈を生かせば、かなり大きな街に育つ予感がする。