2024/01/09/火
寄稿:メディヴァの歴史
無人島に街をつくれ ー 先駆者列伝17:先例なき取り組み、次々と
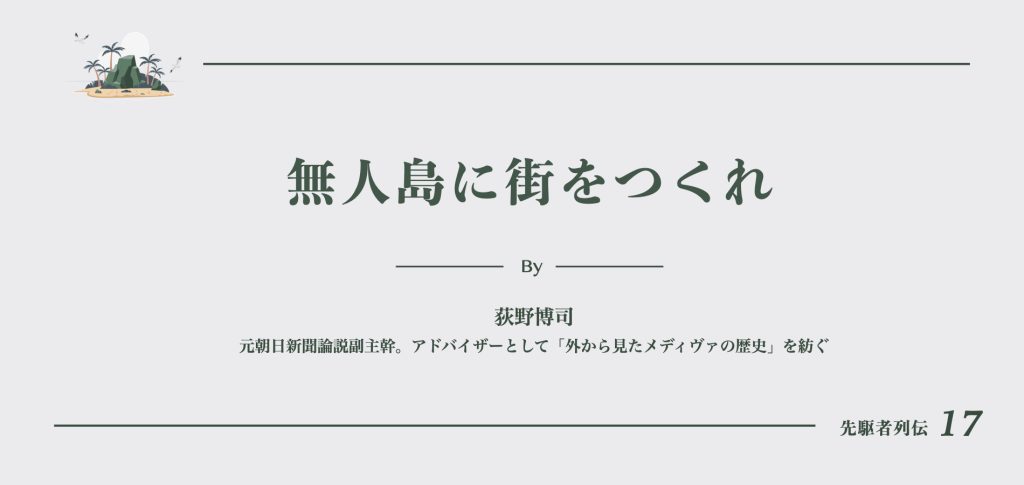
新型コロナで積み上げた知見は、オンライン発熱外来に結実する。コロナは波によって様相が変わったが、22年半ばからの第7波は感染力がきわめて強く、発症者が急増していた。
世田谷区から協力の要請があったのは7月下旬だった。このころ、区の発熱相談センターには毎日600件ほどの電話が入っていたが、100人以上は医療機関が満杯で受診できない。こうした受診難民の受け入れ体制を考えてほしいというのだ。
対面での発熱外来を受けられない人からの申し込みを受けて抗原検査キットを自宅に届け、直ちに自己検査をしてもらう。その結果をもとにオンライン診療し、医師の指示で処方薬をバイクで届けるという作業の流れと人員体制を2週間で整え、8月10日には業務を始めた。用賀アーバンクリニックの入るビルの3階、メディヴァ事務室を間借りしての旗上げである。プラタナスのオンライン診療部門として「プラネット・オンライン診療サービス」という名前も付けた。
まさに綱渡りでの準備作業だったが、担当した浅野悠さんはそれまでの蓄積から「できる自信はあった」と振り返る。全国でも前例のない取り組みは注目を集め、テレビカメラが取材に入り、世田谷区にとどまらず政府や他の自治体からの問い合わせや見学者が続いた。
地味なようだが大きな効果を発揮したのが、入力システムの改良だった。厚労省が運用している感染者の情報把握・管理支援システム(HER-SYS)は入力に大変な手間が掛かり各地の医療機関が悲鳴を上げていた。この入力の自動化を実現したのだ。問診票から必要なデータを拾って瞬時に処理し、カルテも自動作成する。手作業ならば熟練者でも患者1人分に10分はかかった仕事である。メディヴァのシステムチームが設計にあたり、メーカーも社会的な意義があるとして積極的に協力してくれた。
開始から12月までの診療件数は2571件、その4分の3にあたる1935件が陽性者だった。1日に160件をこなしたこともあった。50歳代までの働き盛りの受診が多く、この層をオンライン診療が引き受けたことにより、重症化しがちで対面での診察が欠かせない高齢者に必要な治療を受ける余地を作ったのは確かだ。
筆者は最も忙しい時期にオンライン発熱外来の現場に入る機会があった。
大会議室ほどのフロアに受付、カルテ作成、処方薬準備、発送と分けられた大きな作業スペースが作られ、空いたところに医師がオンラインで患者に向かい合う仮設ブースが4つ設けられている。常時25人ほどが詰め、配送担当者が忙しそうに出入りする光景から浮かんだ言葉は「野戦病院」だった。
どうにかコロナ禍は下火となったが、オンライン発熱外来は新たな医療の実践の場に衣替えする。インフルエンザの流行にも備える体制に移行した12月からはプラネット・アーバンクリニックとして小児科の対面診療もする臨時診療所として独立した。そこには、新型コロナとインフルエンザの同時流行で地域の小児クリニックがパンクする事態を恐れる世田谷区の働きかけがあった。
場所探しでは苦労させられた。当初は保健事業部が三軒茶屋に移ることで空く、隣のビルの一室を使おうとしたが、大家さんが許可してくれない。用賀周辺の物件探しが難航するなか、「野戦病院」として間借りしていたフロアを占領し、逆にメディヴァの事務室を隣のビルに移すという窮余の策に。診療所となれば、診察室や検査室、急患用の予備室なども整えないとならない。プロジェクトチームを立ち上げ、2週間ほどで引っ越しから診療所の内装までを済ませた。
医師会からは患者を奪われると警戒されたようだが、あくまでも各クリニックで対応できない事態での受け皿であり、患者さんにはカルテを渡すので、かかりつけ医にも医療情報が得られるようにする。そんな説明で納得していただいた。最後には医師会側から「これで私たちは年末、年始を休める」という声も上がったそうだ。
23年3月までは臨時施設だったが、4月には常設のプラネット・アーバンクリニックに衣替えしている。オンライン診療の利点を生かして、医療機関に通うのを敬遠したり、定期的な診察を止めてしまったりする人を積極的に受け入れるほか、健康経営の一環として企業のオンライン診療所の役割を果そうとしている。新型コロナの知見を活かした試みからは新しい街の息吹が感じられる。
もう一つ新たな試みがあった。夏のように医療機関の発熱外来が対応できなくなる事態も想定して、新型コロナとインフルエンザの同時検査ができる臨時検査会場を設置した。人口と世帯数は東京23区で最大、面積では第2位という広大な世田谷区をカバーするため、千歳船橋、世田谷、下北沢の3地区に置き、22年12月から翌年3月まで活動した。
当時、インフルエンザは新型コロナと異なり、検体の自己採取が認められていなかった。そこで看護師を配置して、実際の検査と医師によるオンライン診療とをつなぐ仕組みを考案した。各会場に医師を派遣しなくとも効率的で機動的な医療ができるわけだ。医療サービスが届きづらい遠隔地で取り組まれている「D to P with N」のメディヴァ版である。
4年間の長丁場も、今になればあっという間だった気がする。この間、オンライン発熱外来のような革新的な取り組み以外でもメディヴァやプラタナスのメンバーは新型コロナに挑んできた。爆発的な感染を前にして、できることを一つひとつ実践していった例をいくつか紹介したい。
在宅医療部は、自宅や施設にいるコロナ患者への訪問診療を続けて、地域の医療を支えた。21年夏、重症者が急増して入院ベッドの空きがなくなり医療崩壊をきたすなか、桜新町アーバンクリニックは玉川医師会に呼びかけ、自宅療養者の往診支援を開始した。同院を含む日ごろから在宅医療に積極的な診療所3カ所が拠点となり、訪問看護ステーション、訪問薬局の協力を得て酸素機器や点滴などを施す「自宅入院」の仕組みを作った。対象は入院が必要な中等症レベルでありながら自宅で待機させられている患者だ。8月のピーク時には連日5、6件、時にはそれ以上の往診依頼が保健所から舞い込み、在宅用の酸素機器が足りなくなるほどだった。
施設在宅部では機能がパンクしている保健所に代わり、青葉アーバンクリニックの長瀬健彦院長が自ら施設に出向いてコロナ患者を診た。医師本人が濃厚接触者となり出勤できない場合にはオンラインで診療にあたるなど、入居者への影響を最低限に抑える工夫をした。
また桜新町、鎌倉アーバンクリニックなどの外来部門は大量のワクチン接種をしている。外来フロアでは収容しきれず、近くのホールを借りるようなこともあった。感染防止のため、訪問診療での事務ではカルテの確認から算定まで在宅で処理する仕組みを導入した鎌倉アーバンクリニックのように、それぞれが知恵を絞っている。イークは正しいコロナ知識の啓発のために、有楽町院の木下美香院長が作ったパンフレットを健保組合、企業、受診者に配り、感謝された。
メディヴァとして集団接種や検査、オンライン診療などに動員した臨時の医療職や事務スタッフは400人以上に達している。医療職では1週間で100人を超す応募が集まったこともあり、自分たちが培ってきたネットワークの広がりと強さを確認することになった。これからも生きる新たな人脈が生まれた。
いま大石さんは専門委員として規制改革推進会議の議論に加わっている。感染爆発を前にした「緊急時の時限的措置」を機にオンライン診療は社会に定着したように見えるが、時限措置が終わった今、できることは後退している。例えば、職場での受診は認められても、公民館やデイサービスでの実施は難航してきた。これらを一つ一つ取り上げ、医療の世界にそびえる規制の壁を破る作業が続いている。
最後に私事を付け加えることをお許しいただきたい。筆者は21年8月に新型コロナで50歳の従弟を失っている。高齢者ケアの事業を手掛け、お年寄りの感染防止やワクチン接種の送迎に走り回っているなかで感染した。重症の肺炎になり、人工肺(ECMO)の空きが見つかった千葉県銚子市の総合病院まで松戸市の自宅から緊急搬送されたが、回復はならなかった。後には奥さんと高校受験を控えた娘さんが残された。
ワクチン接種の機会が様々な形で用意され、オンライン診療がもっと身近だったなら、こんな悲劇は起こらなかったのではないか。メディヴァ、プラタナスの体験が感染症医療を前進させ、今後も予想されるパンデミックとの闘いに活かされることを願わずにはいられない。