RECRUIT BLOG
2023/07/24/月
寄稿:メディヴァの歴史
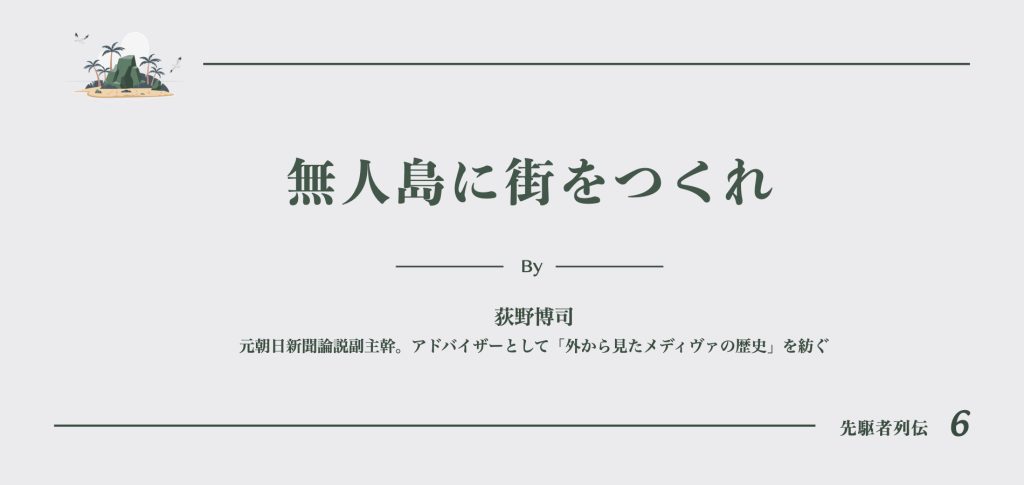
創業の地を東京・世田谷区にしたことは間違っていなかった。たしかに49万世帯、92万人が住む区内には医療施設が多く、病院やクリニックの競争激戦地である。一方で政治や社会問題への関心が高い住民が多く、8年前には同性パートナーについて、パートナーシップ宣誓の制度が始まっている。
こうした先進性は医療や介護の世界にも生きている。20年10月に施行された「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」は、認知症になってからも、区民が自分らしく暮らし続けられる社会を築くことを宣言し、行政は地域団体や関係する機関と手を結び、見守りや緊急時の支援のための活動を支援することを定めている。首都圏初の認知症条例として注目された。
「患者視点での医療改革」を掲げ、家庭医を目指してきたメディヴァ、プラタナスのホームグラウンドには打ってつけの土地柄と言える。在宅治療を早くから手掛け、住み慣れた地で最期を迎えられる環境づくりに努めてきたメンバーの出番が増えるのは当然の流れだった。
その一つが「認知症在宅生活サポートセンター(略称にんさぽ)」である。桜新町アーバンが運営を任され、保健師や看護師、作業療法士、精神保健福祉士ら10人が区立保健医療福祉総合プラザ1階のオフィスに詰めている。
認知症の心配がある当人や家族の相談窓口となる地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター、略称あんすこ)と連携し、まず看護師や作業療法士が訪問して、体調や物忘れの進み具合をチェックする。その状況に応じて、薬剤師や管理栄養士が訪問するほか、医師も本人と会って状態を確認。希望を十分に聞いたうえで、これから必要なサービスを考えていく仕事だ。早い段階から手を打つことで、自宅に住みながら介護や支援を受けられる態勢を整えるのが狙いである。こうした専門家集団は初期集中支援チームと呼ばれ、桜新町アーバンの人材の厚みが生きている。
政府は2012年に「できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける社会」の実現を目指す5か年計画(オレンジプラン)を打ち出した。「認知症の人は、精神科病院や施設に頼らざるを得ない」という旧来の考え方を改めたのだ。失敗を認めたがらない行政には珍しく、それまでの誤りを率直に認めたことは大きな波紋を呼んだ。
同じ年、初期集中支援チームの試行モデル事業の対象に桜新町アーバンが選ばれていた。指定されたのは全国で3カ所だけ。最初の年は10例が対象となり、そのうち5例が認知症と診断され、介護保険サービスの利用、家族の負担軽減、入院などにつなげた。翌年も50例を扱い、得られた知見や成果はその後の全国展開に生かされた。
当時、桜新町アーバンに在籍し、モデル事業を担った医師上野秀樹さんは「認知症ケアはあらゆる社会資源の投入による生活支援であり、医療の役割はその下支えであるべき」と述べている。前々回に紹介した遠矢さんと同じ視点だ。
10年度から独自に「認知症高齢者見守り訪問事業」を始め、看護師が定期的に訪問してきた実績をもつ区が、20年4月に区独自の組織として発足させたのが「にんさぽ」である。センターの管理者を務めている保健師の永野富美子さんによれば、業務のうち3割を初期集中支援チームの活動が占め、残りは区内28カ所の「あんすこ」に配置されている認知症専門担当員の研修や講演会に充てている。認知症への向き合い方を区民全体に考えてもらう推進役への期待は大きい。
永野さんは「遠矢先生の梅干しの体験談から大きな影響を受けた」と話す。遠矢さんがお母さんの介護のために故郷の鹿児島に戻り、地元で医師の仕事をしたときの話だ。認知症スケール(HDS-R)が30点満点で一桁という重度の認知症の女性が一人で暮らし、毎年、梅干しを漬けているのに感銘を受けたと聞かされた。ともすれば、入所や入院を考えがちだが、本人は新しいことは覚えられなくても、昔からやっていたことはできる。住み慣れたところで、周りの支援を受けながら暮らすことの大切さを教えられた。
在宅医療の蓄積はもう一つ、新分野を開拓した。こちらは「かんたき」、看護小規模多機能型居宅介護の略である。医療、介護の世界は、かな4文字が好きなようだ。
胃ろうや吸引などが必要な患者は介護サービスを受けようとしても、並行して医療管理が必要となる。このためデイサービスやショートステイ先を見つけるのは一苦労だった。ガンの緩和ケアを受ける人も同じだ。そこで考えられたのが、専門の看護師もいる施設だった。訪問、日中のデイサービスに加え、介護している家族の都合や負担軽減のために、必要ならば泊まってもらうこともできる。
プラタナスが運営するナースケア・リビング世田谷中町は、17年5月にNTT東日本社宅の跡地の再開発事業「世田谷中町プロジェクト」で生まれたコミュニティプラザの一角でサービスを開始した。介護保険の改正にあわせて12年に「かんたき」が制度化され、プラタナスでも看護師らから「私たちもやりたい」との声が上がったものの、なかなか適地が見つからなかった。再開発を担った東急不動産は分譲マンションだけでなく要介護者も入居できるシニア住宅を建てた。地域住民は、高齢になって介護が必要になればシニア住宅に移り住むことも、そのまま訪問サービスを受けつつ自宅に住み続けることも選べる。「かんたき」は自宅で住み続ける人々にとってはいざという時に頼りになる存在となった。
平日の正午前に伺ってみた。ベッドで寝ている人、介助を受けながら昼食を摂る人、本を読む人、利用者はさまざまな過ごし方をしてくる。ほかに自宅で訪問サービスを受ける利用者もいる。ケアマネジャーの大場哲也副所長によれば、10人ほどの常勤スタッフに加え、桜新町アーバンの訪問診療、訪問看護部隊が全面的にバックアップしていることが安心感につながり、問い合わせが多い。
ここでは当初から認知症への対応を考えたデザインを取り入れている。トイレの扉や風呂の手すりは認知症の人が見ても分かるようにし、認識してほしくない外部への扉は逆に分かりにくく、各部屋の壁は迷わないよう色を変えている。世界の研究をリードしている英スターリング大学の研究成果を応用した。玄関には同大学の認知症サービス開発センター(DSDC)から「金の認証」を受けたことを示す認定証が飾られている。
利用者にお話を聞いた。貫田直義さん。元はテレビ東京の敏腕プロデューサーで、少子長命時代をテーマにした特別番組を制作したこともある。頑健なテレビマンが不調を感じたのは70歳になった頃だった。大好きなゴルフや麻雀が急に弱くなり、家では寝ていることが増えた。不眠や食欲不振で体重は80キロから65キロに落ちた。
脳に委縮が見つかり、何人もの医師に相談したが、「異常なし」だったり「うつ病の可能性がある」だったり。20年春に区内の認知症専門医からレビー小体型認知症と診断されるまでに思わぬ回り道をした。この病気の特徴に幻視があり、貫田さんは夢と現実が入り交じった体験を、夢が重要な役割を果たす人気アニメ『鬼滅の刃』のようだったと振り返る。
復調のきっかけの一つは、世田谷中町の「かんたき」で目にした情景だった。
ケアマネジャーの指導で水曜と土曜はかんたきのデイサービスに行き、月曜は訪問介護や訪問看護を受けている。時間がゆったりと流れるなか、ジャーナリストの目で施設や入居者の様子を観察することが少なくない。そこで気が付いたのが「命の輪廻」。命の糧であるご飯をお年寄りの口に運ぶ職員、それを懸命に呑み込むおばあさん。二人の真剣勝負のような姿に感銘を受けたという。元気に話す80代、90代と接することで、心も体も休まったという。
貫田さんの病気は一進一退を繰り返す。最近は体重が落ちてきているが、請われれば講演もいとわない。旧知の医療ジャーナリスト大熊由紀子さんは、自らが教授を務める大学院の授業やゼミに招き、認知症について語ってもらっている。大熊さんは希望条例の生みの親の一人で、区認知症施策評価委員会の委員長でもある。貫田さんは委員として招かれ、患者の視点から積極的に発言している。身近に認知症の患者はいないため、発症するまではとても遠い世界だったが、今は「数多く(対策を)打て。これからも患者の人数は増えるのだから」と強く訴える。
桜新町アーバンは外来と訪問診療に加えて、訪問看護、ケアマネジメント、デイサービスと多くの職種を一体で運営している。在宅治療の患者数500人ほど、年間看取り件数は150件という実績がさまざまな気づきを生み、社会の急速な変化という追い風もあり、新たな取り組みにつなげてきた。しかも周囲の人々を巻き込みながら、活動は広がっている。
街が大きくなる中で、郊外にはいくつもの共同体ができつつある。