RECRUIT BLOG
2023/05/12/金
寄稿:メディヴァの歴史
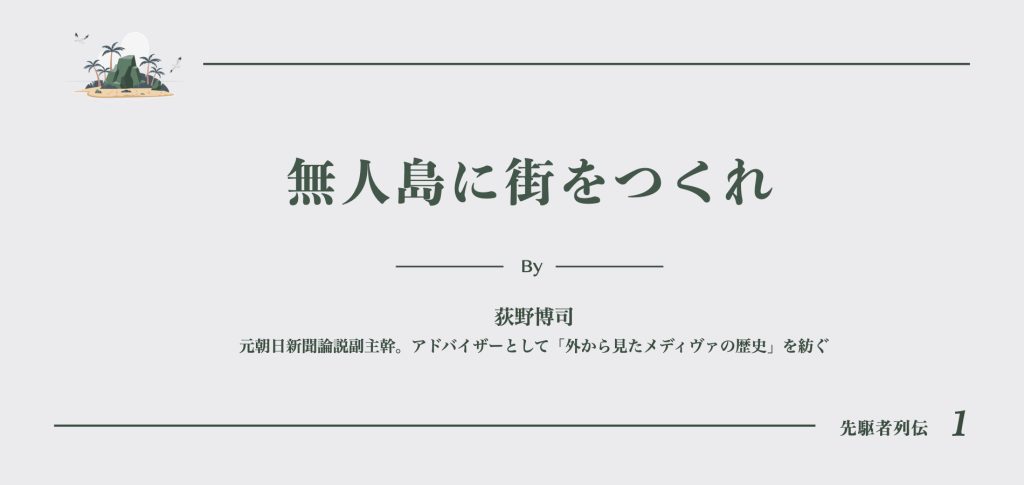
大海原のど真ん中。何が潜んでいるか分からない孤島に真っ先に乗り込み、生い茂った樹木を薙ぎ払って生活の場を懸命に切り開く。そんな向こう見ずは、難破船から命からがら逃れてきた船乗りか、好奇心に満ち溢れ恐怖さえ忘れてしまう探検家の役回りだろう。
医療や介護の世界で次々とチャレンジを続けているメディヴァが目指すのは『無人島に街をつくる』。たしかに少しずつではあるが町や村が出来上がりつつある。では、どんな面々が開拓物語を紡いできたのか。これまでの歩みをたどってみよう。
・・・・・・・・・・・・・・・
この人がいなければ、私たちがこの地に足を踏み入れることはなかっただろう。まずは島の設計図を今なお描き続け、陣頭指揮で道を切り開いている大石佳能子さんの話から始めよう。
社会人のスタートを切ったのは、大阪御堂筋にそびえる日本生命本社である。1980年代前半、雇用機会均等法などない時代に大学出の女性を採用しようとする会社は極めてわずかだった。「さてどうしようか」。大企業の本社ビルが並ぶ大通りを歩いていると、日生の玄関に掲示された「大卒女子募集」の看板が目に入った。外回りのセールス部隊「生保レディー」の募集とは知らずに飛び込んできた元気な女学生をどう扱うのか。幸いだったのは、保守的な銀行や生保も試行的に大卒女子を正社員として採ってみる動きが始まっていたこと。大阪大法学部の学歴もものを言ったのか、飛び入りながらこの枠に滑り込めた。
不動産部に配属され、お仕着せの制服で会社勤めを歩み出した。海外グループに入ったおかけで国際的な不動産投資の動きが学べ、結構面白かった。しかし1年ほどで仕事が終わってしまう。国際業務は東京に集約するという経営コンサルの提案を受け入れ、職場そのものが大阪から移ってしまったからだ。「東京に行かせろ」と騒いだものの聞き入れてもらえるはずもない。
これがその後の人生に深くかかわるマッキンゼーとの最初の出会いとなった。
新たな職場はALPS開発部。要は商品開発部だが、この珍妙な組織名もマッキンゼーの提案によるものだったと聞く。米国や欧州で進む金融革命の波は日本にも打ち寄せ、遠からず国境も業界の壁も乗り越えた大競争が始まることは確実だった。お堅い日生らしからぬ組織が誕生した背景には、そんな危機感があった。ちなみにアルプスはAsset、Liability、Protection、Serviceの頭文字をつないだものである。養老保険や死亡保険が主体の老舗生保を、保障や資産形成などを幅広く支える総合金融サービス業に脱皮させる狙いが込められていた。
仕事の合間にお茶くみもする「アルプスの少女」の毎日は工夫次第で面白くもなる。上司に恵まれたことで比較的自由に働かせてもらった。生保会社にふさわしい新分野の開発を企画し、老人ホームやスポーツクラブを訪れ、東京で開かれる勉強会に参加した。忘れられないのが、ニッセイ基礎研究所が東京で開いた高齢化セミナーだ。80年代は団塊世代が社会の中核を占め、世界第2の経済大国としての自信と活気がみなぎっていた。その先にバブル景気の熱狂が待ち構えていた時期に、いずれ迎える少子高齢化への備えや健康寿命の考え方を知り、真剣に向き合う機会を持ったのは、今に生きる大きな収穫だった。
総合職制度も導入され、そこそこ面白い会社勤めへの疑念が湧いたのは社員食堂でいつものように昼食をとっている時だった。ふっと浮かんだのは「自分はここにいて年をとっていくのかな」。頑張れば広報部長ぐらいはなれるかもしれないが、それでいいのだろうか。そのころ、仕事で知り合ったのが、米国留学から戻ってきた投資銀行の不動産担当者だった。国内ではMBAはまだまだなじみの薄い時期だったが、最先端の経営や金融について、実際のケースを踏まえて考え抜くビジネススクールの話に魅力を感じたという。
両親はともに阪大法学部、当人も堺生まれで小学校は箕面という根っからの関西人である。インタビューでよく飛び出す地元ネタは「出世といえば自分で商売を始めるか、お笑いで成功するか」。その通り、将来は会社を起こすことを考えていた。基礎固めにビジネススクールでの留学体験は悪くないと思い立ってからの行動は早かった。ハーバード、スタンフォード、ウォートン、コロンビアなど米国の名だたる名門校に次々と願書を送った。最終的に最難関のハーバード、スタンフォードから合格の通知が届き、商社マンだった父親について中学2年まで6年間を過ごしたニューヨークに近いボストンのハーバードに進んだ。
男性社員であれば、会社からの派遣留学という道もあったはずだ。今は様変わりだが、80年代後半の著名大学には多くの日本人留学生が在籍し、ちょっとした日本コミュニティーができていた。しかし、女性の派遣など前例がないために認められず、退社しての自費留学の道しかなかった。
ビジネススクールの2年間は思い出しても苦しい日々だった。覚悟してはいたが、課題が半端ではない。徹夜しないと仕上がらないような分量をこなし、授業では教師から容赦ない難問を浴びせられる。気も心も休まるときがなく、「日本人はほとんどが死んでいました」という物騒な描写も誇張とはいえない。成績の低い数パーセントは有無をいわさずに学校から放り出される仕組みだ。さらに学費や寮費、生活費が卒業までに1000万円以上かかる。毎年、900人の学生のなかから自殺者が出るような環境のなか、どうにか中の中程度を維持して卒業することができた。
学費の不足を埋めるためにも、将来の進路を考えるためにも、米国のビジネススクール生にとって1年目を終えた夏休みのインターンは極めて重要である。そこで選んだ先はコンサル業界の最大手マッキンゼーだった。将来の起業を考えれば、さまざまな業界を知る機会があり視野が広がる魅力があった。日生時代の宿縁を意識したわけではないそうだ。
ニューヨークでの実務体験で仕事の面白さに開眼したことで、卒業後はコンサル業界に進むことを決めた。ライバル社にも魅力を感じて迷っていたが、マッキンゼー幹部でハーバード出身の茂木敏充氏らがリクルーターとして現れた。茂木氏は後に政界に転じ、現在は自民党幹事長として絶大な影響力を誇っている。その説得もあって最終的にマッキンゼーへの就職を決めた。88年のことである。
(続く)
・・・・・・・・・・・・・・・・
(筆者敬白)
筆者の荻野博司(おぎの・ひろし)と申します。2月からアドバイザー(パブリック・リレーション担当)という役職に就いています。これから随時、メディヴァの「街づくり」を様々な角度からお伝えします。
もとは朝日新聞の経済記者で、社説や天声人語を書く論説委員も務めました。入社10年目、大阪本社勤めの折に日本生命ALPS開発部を訪れ、神妙な表情で大石さんが出してくれたお茶をありがたく頂戴しました。その後、私はニューヨーク特派員となり、ボストンで学ぶ大石さんや学友の皆さんに留学生事情の取材などで協力いただきました。
2000年の用賀アーバンクリニックの開院では、内覧会のころから折々に顔を出し、地元に根を張り、皆さんに愛される医療機関になっていく姿を目の当たりにしてきました。翌年、筆者自身が予期せぬ水疱瘡で高熱に苦しめられた折には、メディヴァやプラタナスの皆さんにお世話になりました。入院先の主治医は、後に松原アーバンクリニックの院長になられた梅田耕明先生です。
こんなご縁もあり、メディヴァやプラタナスの語り部を務めさせていただきます。