RECRUIT BLOG
2025/03/25/火
寄稿:メディヴァの歴史
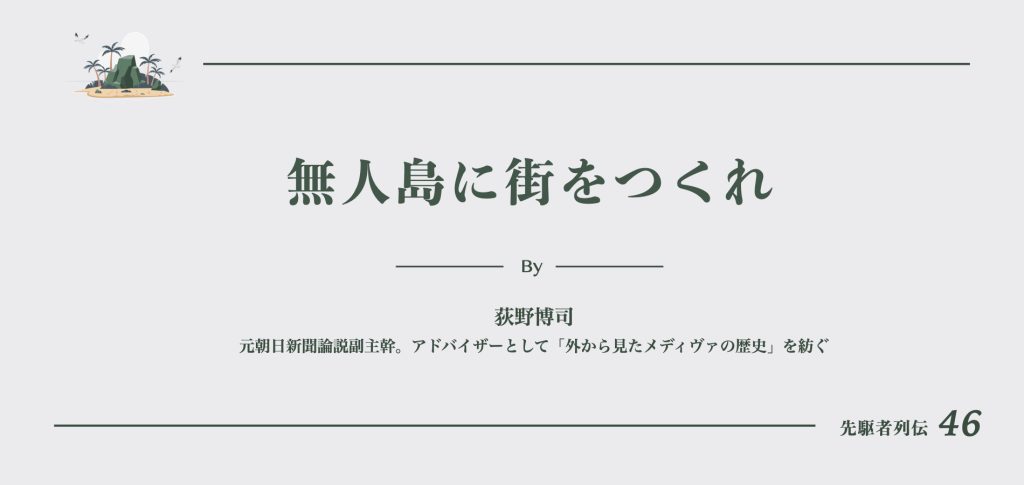
2年ほどにわたって、無人島での街づくりの現場を訪ね歩いてきた。多彩な顔ぶれがそれぞれの土地を切り開き、根を張ろうと奮闘する姿に出会う楽しみを満喫した。
そろそろ島巡りも終わりが近づいている。すべてを伝えられたわけではないが、全くの門外漢である筆者にもメディヴァやプラタナス、シーズ・ワンの皆さんが起こした風が古い仕組みや因習、前例にとらわれた医療の世界を揺さぶっている手応えを感じることができた。
今回、訪れるのは2022年から進めているコミュニティ&コミュニティホスピタル(CCH)事業である。筆者は、この取り組みをメディヴァが積み上げた25年の活動の到達点であり、これからの25年の出発点とみている。
2020年から3年余りにわたり世界を翻弄し、今もその余波が残っているコロナ禍。メディヴァやプラタナスが総力を挙げてワクチン接種やPCR検査、患者の治療に当たったことは連載(16、17回)で紹介したが、信じられないような大混乱の一方でパンデミックの先をにらみ、地域医療の再生を目指す壮大なCCH事業の原型が形作られつつあった。その構想は、取締役の小松さんが長年手掛けてきた病院再生の流れと、大石さんが作ってきた在宅医療・地域包括ケアづくりの流れが合流して生まれた。
小松さんがコロナ以前に温めていた構想は病院再建ファンドの立ち上げだった。その資金をもとに中小病院を集めて改革を一気に進めようという着想である。しかし、社内の賛同は得られない。「中小病院の経営を再建するだけで地域医療に役立つのか」「医療資源の再配分の観点からは、延命させない方がいい病院もあるのでは」「そもそも、そんな話に資金は集まらない」。厳しい意見ばかりだった。
そうこうするうちコロナの感染が始まった。メディヴァの人々にとって病院回りも出張もできないし、話をしたくとも相手の医師は病院から出られない。考える時間が図らずも2倍に増えたうえ、「三密禁止」のなかで当たり前になったオンライン会議が一気に普及し、どんな遠くの人とも気軽に意見が交換できるようになった。浮いた時間で新しい事業構想の検討が始まった。
小松さんの病院再生ファンド構想を元に、もっと意義があり、実現性が高く、その結果、資金調達ができる方法はないか。そのためには、まずは目の前にある社会課題から発想する必要がある。
超高齢社会を迎えている日本の大きな課題は、高齢者が安心して最期まで暮らし続けることができる仕組みをどう創るか、であり、また人口が減っているなかでコミュニティをどう維持するかである。中小病院の再生をテコにこの課題を解くことができないだろうか。
一つのヒントは、10年前に大石さんやシニアマネージャーの村上典由さんが講演会で知り合った本田宜久医師(現、穎田病院院長)の挑戦だった。福岡・飯塚の頴田病院はもとは市立病院だったが、建物の老朽化と4億円の累積赤字、さらに大学からの医師派遣の打ち切りで行き詰った。そこで2008年に地元を代表する麻生グループの医療法人に経営が委譲された。
望まない身売りに、医師や職員が意気消沈している病院に送り込まれた本田医師が目指したのは、地域包括ケアの拠点「コミュニティホスピタル」への転換である。総合診療を掲げて急性期病院と在宅療養の間をつなごうというものだった。総合診療医を中心に組織が一丸となって外来、在宅、入院を一気通貫で診る地域に密着した医療機関を目指した。その結果、経営移譲の翌年には医業利益ベースで黒字に転換し、2010年からは経常黒字が続いている。
当時、大石さんと村上さんには松原アーバンクリニックの有床診療所での経験があった。「自前の病床のある在宅医療」は患者、家族、医療者のいずれにとっても安心感があり地域での在宅医療を促進する要になるとの実感から、在宅医療を担う在宅療養支援病院の将来性を感じていた。それを特定の診療科にこだわらず、患者自身に向き合う総合診療科の医師が担ったならば更に強さは増すはずだ。
本田院長の理念は、頴田病院で学んだ大杉泰弘医師(現、豊田地域医療センター 副院長/総合診療科部長)に引き継がれた。藤田医大が引き受けてコミュニティホスピタルに転換させた豊田地域医療センターを拠点に総合診療医を育成したことで、藤田医大は日本最大の総合診療医局となった。
大杉医師は在宅医療を学びに桜新町アーバンクリニックを訪れたことがある。10年以上前のことだが、すでに遠矢純一郎院長が進める在宅医療の実績は医療界で広く知られており、その内容を学ぼうというものだった。皆で温かくもてなし、細かいノウハウまで提供したことからメディヴァの人々と大杉医師は親しくなっていった。大石さんや桜新町アーバン事務長の村上典由さんとはそれ以来の付き合いである。
コロナ直前に大石さんや小松さん、さらにコンサル部隊の面々で、豊田地域医療センターや総合診療医の育成プログラムを見学に行った。飲み会の機会も持ち、大杉先生とメディヴァが理念を同じくし、それぞれの機能を果たしてwin-winの関係になれるという手応えが感じられたという。大杉先生は更に多くの総合診療医を育てるために、中京地域以外にも拠点となるコミュニティホスピタルを望んでいた。
コロナ自粛のなかでも大杉先生とやりとりをしながら、構想が煮詰まっていったとシニアマネージャーの草野康弘さんは振り返る。「今後の方針について、ファンドや金融機関、事業者、大杉先生と話し合う中で、コミュニティホスピタルを全国に広げたいという話が出てきた」。現在、草野さんは連載(44、45回)で紹介したCCHのパイロットサイト同善会で法人事務局長を務めている。
全国に5800を数える200床未満の中小病院の約半分は赤字だと言われている。その再生を見据え、患者本位で人生に向き合う医療、総合診療医の活躍の場の拡大、地域とのつながりの重視など盛りだくさんの目標を掲げた。中小病院が在支病に転換し、地域包括ケアの核であるコミュニティホスピタルになることで再生は果たすことができる。ただ、病院が立ち直っても地域が衰えていったら、最終的には病院も共倒れである。ホスピタルだけでなく、コミュニティも再生させることを目指し、この取り組みは「コミュニティ&コミュニティホスピタル(CCH)事業」と名付けられた。
2023年夏、CCH事業にあたる100%子会社シーズ・ワンに東急不動産ホールディングス、東京きらぼしフィナンシャルグループなどが3年間であわせて15億円を拠出することも決まった。これまで自力で実績を積み上げてきたメディヴァにとっては大きな挑戦である。
シーズ・ワンは中小病院を再生させるために必要な要素を作り込み、提供するプラットホームとなる。事業内容は①在支病に転換するための助言・指導、②医療事務、労務管理、採用などのセンター処理、③医療現場をDX化するシステム構築やサービス提供等々、盛りだくさんだ。要は、中小病院の戦略的な立ち位置を見直したうえで医療以外のバックオフィス負担を軽くし、再出発を後押しすることだ。シーズ・ワンの運営のため、病院再生の経験を積んだ羽田雅史さんが22年9月にメディヴァに加わった。
さらに総合診療医を育てるために一般社団法人「コミュニティ&コミュニティホスピタル協会(CCH協会)」を立ち上げた。代表理事は米国で家庭医の研修を修めた武藤正樹先生である。大義に賛同してくれた元厚生労働省事務次官の辻哲夫さんも理事に加わっている。大杉先生も理事に加わって頂いた。
協会の事業はCCHへの転換を目指す病院・医療者のネットワークづくりと総合診療医の育成の2本立てだ。前者には最新情報の提供、勉強会や見学会、交流会などの開催のほか情報交換ができるオンラインコミュニティの運営があり、CCHに関心をもつ全国の中小病院や医療者の交流や勉強の場を目指す。
各CCH病院は総合診療医をめざす若者の研修の場としても活用することになり、すでに同善会病院や水海道さくら病院などで専門医を育成するプログラム「CCH総診」が始まっている。
若手の医師が総合診療医になるためのプログラム提供とともに、他科の専門医が総合診療を修めるリカレント教育にも力を注ぐ。総合診療、他科の専門性、DXを含むマネジメント能力の3つの力を持った「π字型人材」の育成を目指す。
こうやって育った多くの人材にとって、CCH病院は活躍の場になることが期待できる。今までは総合診療医には大病院の中で横串的に機能するホスピタリストか、開業するしか選択肢が無かった。オプションとして中小病院が加われば、個人のキャリアイメージも広がり、後継者難の解消にもつながるのではないか。
さまざまな人々が抱えてきた問題意識やアイデア、人とのつながりが、コロナの感染拡大という激動のなかで患者の人生を診るCCH事業に結実したといえる。
良いこと尽くめの構想だが、医師や看護師など多くの医療専門家と事務スタッフで成り立つ医療の現場を改革するのは一朝一夕に進まない。その現実には、メディヴァやプラタナスの人々は何度も直面している。意欲的で時代を先取りしたアイデアを盛り込んだCCHではなおさらのことである。
次回は、現場でCCHに取り組む人々の声に耳を傾け、壮大な構想を社会に広げるための課題を考えたい。
(つづく)